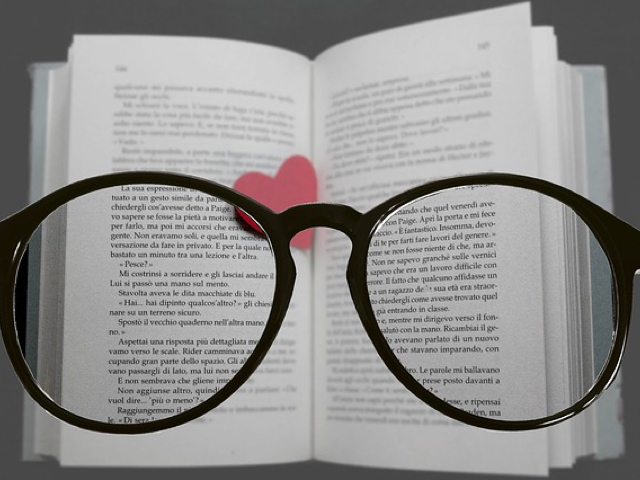沈黙の臓器・肝臓でよく起こる病気とは?肝炎が進行すると肝硬変、肝がんなどになりやすい?!
2020年11月2日
50代以降の女性に多い骨粗しょう症ってどんな病気?骨粗しょう症の予防方法、おすすめのサプリはある?
2020年11月14日
痛風はその病名通り「風が吹いただけで激しい痛みが走る…」と言われていますよね。
風が吹くだけで痛みがでるなんてどんな病気なの?と恐ろしく感じている人もいるはず。
しかし実際には、痛風についてどんな病気なのかよく知らない人が多いです。
ここでは痛風とはどんな病気なのか?どんな症状がでるのか?
痛風になる原因や予防対策の仕方などを分かりやすく解説していきましょう。
目次
【痛風とはどんな病気?痛風は潜伏期間を経てから発症するって本当?】
痛風とは尿酸塩結晶によって関節に炎症を起こす疾患のことです。
血清尿酸値が7㎎/dlを超えた状態が継続すると、血液に溶け切らなかった尿酸が結晶化してしまいます。
結晶化した尿酸は関節に沈着し、何らかしらの原因で関節の中で剥がれ落ちます。
この剥がれ落ちた尿酸塩結晶を異物として認識した白血球が排除しようとすることで炎症が起きてしまうのです。
初めて痛風発作が発症するまでには5年以上、尿酸値が7mg/dlを超える高尿酸結晶の状態が続きます。
つまり痛風は5年間という潜伏期間を経て発症するということ。
健康診断の結果などで尿酸値を定期的に確認しておけば痛風発症前に予防できるでしょう。
痛風=激痛があるというイメージを持っている人は多いでしょう。
また、外食や飲酒が好きな人がなりやすい、中高年が発症しやすいというイメージを持っている人もいるかもしれませんね。
実際のところ、痛風は誰でもかかる可能性がある「生活習慣病」の1つなんです。
成人男性の5人に1人は痛風予備軍と言われているほど、身近な病気となっています。
さらに最近では食生活の変化によって20~30代の若い世代でも痛風になる可能性は高まっているんです。
また、痛風を患っている人は、高脂血症や高血圧症などの他の生活習慣病を併発している可能性が高く、脳梗塞や動脈硬化などの合併症を引き起こしやすいとも言われています。
痛風は発症すると長期にわたって治療を行わなければなりません。
誰でもなる可能性のある「痛風」に関して知識を持っておくことで発症を予防できるでしょう。
【痛風は男性の方がなりやすい?】
痛風は男性の方がなりやすいと言われています。
これは男性の方が体内の尿酸量が多く、女性ホルモンには尿酸を排泄する働きがあるため患者数は男性が多くなるためです。
近年では食の欧米化や生活習慣の乱れによって、女性の痛風患者さんが増えてきている現状があります。
【痛風発作が起こるきっかけとは?】
痛風発作はある日突然起こります。
発作が起こるきっかけは様々で、激しい運動で起こす人もいれば、わくわくするプラスのストレスや、つらいことでのマイナスのストレスが積み重なって起こす人もいます。
またサウナに入っていて痛風発作を起こした人もおり、急激な尿酸値の変動によって引き起こされるのです。
体の中で作られる尿酸の量と、体の外へ排出される尿酸の量のバランスが崩れると、尿酸値が高くなり、尿酸塩結晶ができやすくなるでしょう。
【痛風の症状とは?発作前に症状が出ることもある?】
痛風はどのような症状を引き起こすのでしょうか?
痛風の主な症状は「足の親指の付け根に激しい痛みが起こる」です。
激しい痛みが急激に襲ってくるのが特徴になります。
また、足の親指の付け根以外にも、足の甲、足関節、膝関節、手関節、肩関節などに痛みがでる場合もあります。
この激しい痛みが出た状態を「痛風発作」と呼び、この痛風発作の痛みは風が吹いただけでも痛いと言われるほどの耐え難い激痛です。
ただ痛みは発作的に起こるため、しばらくすると治まります。
激痛のピークは24時間後と言われており、そこから3~7日ほど経過すると痛みは引いて歩けるようになります。
この痛風発作と痛みが治まる「鎮静」を繰り返すうちに症状が悪化して、関節の腫れがひどくなってコブ状になったり、痛風腎や腎臓結石・尿管結石などの他の病気を併発したりすることもあるのです。
痛風腎になると、腎臓に尿酸結晶が溜まり、腎機能が低下して、排泄が正常に行えなくなります。
また、人によっては痛風発作の前兆の症状が現れる場合もあります。
前兆の症状としては「関節の違和感、ムズムズ感」が多く、痛風発作の前兆期とも呼ばれているのです。
この前兆期は夜間に感じる人が多いそうです。
【痛風の検査・診断方法とは?】
痛風の診断は、足の親指の付け根に痛みがあるかなど、痛風に特徴的な症状が見られるかをまずは確かめます。
また痛風の前段階である高尿酸血症(血液中の尿酸値が異常に高い病気)であるかどうかも重要な判断基準となるので血液検査をするのが一般的です。
ただ痛風発作が出ている場合、血液中の尿酸値は低くなる傾向があるため、痛みのある患部から関節液を採取して、その液中に尿酸塩結晶があるかどうかを調べる検査を行う場合もあります。
この関節液検査をすれば、偽痛風や外反母趾など、痛風と似た症状の病気と鑑別することができ、確定診断が可能です。
【痛風の治療方法とは?】
痛風発作が起きている場合、患部を心臓より高くして冷やしながら安静にします。
患部を温めたり、もんだりすると痛みが増強するのでしては×。
痛みや炎症が強い時には、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAID)で痛みと炎症を抑えます。
痛風発作が治まったら、尿酸値を下げる治療をスタートしていきます。
痛風の痛みが消失して2週間以上経過してから、尿酸降下薬の内服をするのが一般的です。
薬物療法とともに、生活習慣の改善も行っていきます。
食べ過ぎに注意して、プリン体を多く含む食品や、アルコール摂取を控えるようにしましょう。
また、過度な運動は尿酸値を上昇させてしまうので、負荷の低い運動にとどめるようにします。
発作の前兆期(ムズムズ感、関節の違和感)には、コルヒチンという薬で発作を抑えていきます。
コルヒチンを1~2回内服しても発作を抑えられない場合には、痛風発作と同様の治療に移行します。
治療で気を付けておきたいのは、発作が起きているときに尿酸を下げてしまうと却って痛みが悪化してしまうため、発作中には尿酸降下薬は使用しないことです。
【痛風の合併症に気を付けよう】
痛風とその前段階となる高尿酸血症をそのまま放置していると高血圧や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病を併発しやすくなると言われています。
なんと痛風患者さんのうち、半数以上は高血圧、半数は高脂血症を併発しているのです。
中には高血圧と、高脂血症を両方併発している人もいますよ。
また糖尿病の場合、糖尿病予備軍(耐糖能障害)の人に痛風を併発する人が多く見られます。
逆に糖尿病を発症している患者さんでは、尿糖を排出するために尿量が増え、尿酸も一緒に排出されやすいため、痛風患者は少なくなる傾向にあります。
痛風や高血圧、高脂血症になると気を付けなければいけない病気といえば「動脈硬化」です。
痛風は血液中に尿酸が増え、高血圧では血液の圧力が高まります。
どちらの症状も血管に大きな負担を与えており、その状態が長く続くと血管機能が低下し、動脈硬化を引き起こしやすくなるのです。
痛風や高尿酸血症をそのまま放置していると、高血圧になり、そこから動脈硬化を起こし、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる重篤な病気へと進みやすくなるでしょう。
【痛風の原因となる尿酸ってなんなの?】
痛風の原因となっている物質といえば「尿酸」ですね。
尿酸は遺伝子を構成するDNAと情報を伝達するRNA、エネルギーを担当するATPが分解される際に生成される物質です。
尿酸はほとんどの動物では分解され、体内には溜まりません。
しかし人間では尿酸を分解する酵素が遺伝的に欠損しているため、尿酸がたまりやすいのです。
尿酸は人間の体の中に一定量あって、1日に約0.6g作られると言われています。
血液などの体液に溶けて循環して、尿の中で漉しとられて体外へ排出されます。
また一部は消化管からも排出されます。
なんらかの原因によって血液中尿酸の濃度が上昇して飽和濃度を超えると、体の中に蓄積していきます。
溶けなくなった尿酸はナトリウムと塩を作り、結晶化。
尿酸濃度が高い状態が続くと、この尿酸塩の結晶が関節内面に沈着するのです。
痛風発作はこの尿酸塩に対して体の防御機構である白血球が反応して、攻撃する時に起こるのです。
尿酸塩が関節にたまれば痛風発作になりますが、皮下に溜まると皮膚の下に結節ができます。
これを「痛風結節」と呼んでいます。
痛風結節は脊髄にたまり、神経症状の原因になることも。
体内の尿酸の量は血清尿酸値で知ることができます。血清尿酸値は痛風を診断する上で1つの指標となります。
血清尿酸値は男女ともに7.0mg/dL までは基準値内で、これを超えると異常で高尿酸血症と呼ばれます。
【痛風になる原因は?】
痛風になる=尿酸値が高くなる原因は様々です。
大きく分けると遺伝的要因と環境要因があると言われています。
それぞれの原因についてまとめてみましょう。
<遺伝的要因>
血清尿酸値を変化させる要因には遺伝的なものがあります。
ただ遺伝子の変異を持っている人はまれで、大多数の痛風や高尿酸血症には関係しません。
遺伝子研究では、痛風の発症に関わる遺伝子が複数発見されており、遺伝子による代謝異常がある人は痛風や高尿酸血症になりやすいです。
家族に痛風患者さんがいる場合、痛風になりやすい遺伝子を持っている可能性も高いですし、食生活が似ているケースも多いため、若くても注意が必要でしょう。
<環境要因>
痛風の要因はほとんどが環境要因となります。
代表的な環境要因をまとめてみましょう。
・食生活
食事内容など食生活の問題は、尿酸値に大きく影響をもたらします。
肉食は痛風を増やし、海産物も痛風を少し増やすと言われています。
逆に野菜や乳製品は痛風を減らすことが分かっています。
レバーや白子、あん肝、魚の干物などは尿酸を作る成分となるプリン体が多いです。
またプリン体は水に溶ける水溶性の性質があるため、肉や魚から取った鶏ガラスープなどにも注意が必要です。
ラーメンのスープなどは残すようにしたいですよ。
また鍋の煮汁で締めにおじやを作る場合がありますが、これは痛風患者さんにはよくありません。
魚卵は基本的にプリン体が多いイメージがありますが、イクラ、筋子、数の子などはプリン体が少な目です。
また砂肝も内臓系ですがプリン体は少な目ですよ。
・肥満
痛風の患者さんの60%は肥満であると言われています。
肥満度が高くなると尿酸値も上がります。
食事量を減らして、運動を積極的に行い、標準体重を守ることが重要でしょう。
肥満は体内でのプリン体の合成を促進させ、尿酸の排泄機能を低下させてしまいます。
肥満の原因となる砂糖を多く含む清涼飲料水の飲みすぎや、動物性食品の摂りすぎも尿酸増加につながるでしょう。
尿酸は体内で生成されるものが全体の8割を占めているので、食品でのプリン体摂取を気にするよりも、尿酸を必要以上に生成しない適正体重を維持することが重要になります。
・飲酒
アルコールを摂取すると尿酸値は一時的に上昇します。
これはアルコールが体内で分解される際に尿酸が作られるためです。
また尿酸が作られる際にできる乳酸には、体内に尿酸を溜める作用があるため、尿酸が蓄積しやすくなってしまうことも原因となっています。
さらに一部のアルコール飲料にはプリン体が多く含まれています。
このプリン体は尿酸の元となる成分であり、プリン体を過剰に摂取することで痛風を発症しやすくなるともいわれているのです。
ちなみにプリン体はビールに最も多く含まれており、焼酎、ブランデー、ウイスキーなどの蒸留酒にはあまり含まれません。
ビールをたくさん飲むと痛風になりやすく、同じアルコールでもワインは痛風を減らすことが研究結果からも分かっていますよ。
・腎臓の機能低下
腎臓の機能が低下していると、尿酸を正常に処理できなくなります。
すると体内では尿酸量が増加してしまうでしょう。
腎機能は年齢とともに低下していきます。
また、高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満なども腎臓に負担をかけてしまうので気を付けなければなりません。
水分補給をしっかりと行い、排泄を促してあげることも大切です。
・筋肉運動
激しい筋肉運動は尿酸値を上昇させてしまいます。
特に短時間で激しい運動をすると、無酸素運動になるため尿酸値が一時的に上昇してしまうでしょう。
逆にジョギングやスイミングなど有酸素運動であれば、尿酸値の上昇は比較的軽いので特に影響はありません。
・ストレス
過度なストレスや、過剰な知的仕事は脳活動を活発にするため、尿酸値が上昇すると言われています。
実際にストレスを受けたり、疲れていたりすると尿酸値が高くなることが研究結果からも明らかです。
これは血管を収縮させ、腎臓の働きを低下させてしまうためと考えられていますよ。
ストレスは腎臓の負担となり尿酸を増やします。飲酒量や食事を改善しても尿酸値が下がらない場合はストレスが関与しているでしょう。
ストレス解消法を見つけてストレスをため込まないことが大切です。
・脱水状態
発汗や下痢など脱水状態になると、血清尿酸値は上昇します。
こまめに水分補給をして尿の排出を促すことで、尿酸値の上昇を抑えることができます。
・他の病気の影響
腎機能が低下している場合や、血液の病気を患っている場合、尿酸値が上がるケースが考えられます。
また悪性腫瘍が原因で高尿酸血症になることもあるのです。
逆にパーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマー型認知症などでは血清尿酸値が低くなると言われています。
・薬剤の影響
服薬している薬剤によっては尿酸値を変化させる場合があります。
尿酸値を上昇させる薬剤としては、ループ利尿薬、喘息治療薬「テオフィリン」、サイアイザイド系降圧利尿薬、少量のアスピリンなどがあります。
逆に尿酸値を低下させる薬剤としては高脂血症治療薬、高血圧治療薬などがあります。
【生活習慣の改善が痛風予防には1番効果がある!!】
痛風にならないように予防するにはどうすればよいのでしょうか?
一番の予防策は「生活習慣を改善すること」です。
ここでは痛風予防として心がけておきたいことをまとめてみましょう。
<食べ過ぎに注意する>
肥満は痛風にとっては大敵です。
痛風はかつて「ぜいたく病」とも言われており、食べ過ぎの結果でもあります。
摂取エネルギー(カロリー)を抑えて肥満を解消するだけでも、痛風の原因となる尿酸値は下がるでしょう。
肉や魚の内臓や干物には、プリン体が多く含まれているので食べ過ぎには注意です。
<プリン体の多い食品を続けて摂取しない>
プリン体を多く含む食品を全く食べてはいけないということはありません。
ただ続けて食べないことが大切です。
白子、アンコウの肝、干物類などは特に注意が必要。
プリン体を多く含む食品を食べる時には野菜も一緒に摂取するようにしましょう。
野菜には尿をアルカリ性にして、尿酸を溶けやすくする作用があるので、たくさん食べるのがおすすめですよ。
<調理法、食べ方にも工夫を>
プリン体は水溶性なので、煮たり茹でたりすると水に溶けだし、摂取量を減らすことができます。
プリン体を多く含む食品を調理する際には、煮たり茹でたりする調理法にすることでプリン体摂取を極力減らすことができるでしょう。
<お酒はほどほどに>
アルコールを肝臓で分解する際には尿酸が作られてしまいます。
つまりアルコールを摂取すると尿酸値があがってしまうということ。
特にビールには尿酸の元となるプリン体が多く含まれていることが知られていますよね。
プリン体カットのビールだから大丈夫!といって飲みすぎてしまっては意味がありません。
ビールであれば500mL、ウイスキーなら60mL、日本酒なら1合くらいの量にしておきましょう。
<水はたくさん飲もう!2L以上が理想的>
尿酸は尿によって体外へ排出されます。
つまり尿量が増えれば尿酸をうまく排泄できるということ。
水やお茶をたくさん飲んで尿量を増やすことで、痛風予防につながりますよ。
水やお茶は1日2L以上飲むのがおすすめ。
ただ砂糖を多く含む清涼飲料水は尿酸値を上げてしまうので飲みすぎには注意が必要です。
<ストレスをうまく解消しよう>
ストレスは尿酸値を上げてしまう要因の1つです。
ストレスをうまく解消することで尿酸値を上げないようにできるでしょう。
体を動かす、人と話す、趣味に没頭するなどストレス発散方法は人によって違います。
自分に合った方法でストレスを解消できるとよいですね。
<適度な運動を心がける>
過度な運動や、100メートル奪取、ベンチプレス100キロなどの無酸素運動は、尿酸値を上昇させてしまいます。
痛風予防にはジョギングやウォーキングなど有酸素運動がベスト。
話ながらでもできる負荷の少ない運動がおすすめですよ。
ウォーキングやアクアウォーク、ゴルフなどは肥満解消、ストレス解消にもつながるので痛風予防にぴったりと言えるでしょう。
【痛風予防におすすめの食べ物とは?】
痛風を予防するためには、尿酸値を下げる必要があります。
尿酸値を下げるために腎臓から尿酸を排泄させる必要があります。
尿酸を体外へ排泄するには、尿をできるだけアルカリ性にすることが重要なのです。
アルカリ性食品で代表的なのは
・野菜
・海藻類
・いも類
・米などの穀類
・豆類(豆腐)
・キノコ類
・バナナ
・乳製品
です。
これらの食品を多く摂取すれば、尿がアルカリ性に近づくため、尿酸を排泄しやすくなるでしょう。
次に痛風予防・改善のために効果的な成分をまとめてみましょう。
<乳製品に含まれるカゼイン>
牛乳などの乳製品にはプリン体がほとんど含まれません。
さらに乳に含まれるカゼインとホエーたんぱく質は尿酸の排出を促す作用があります。
乳製品に含まれるカゼインは体内に入るとアラニンという成分に変換します。
このアラニンは酸性尿をアルカリ性にして、腎臓の働きを助け、尿酸を排出させる働きがあるのです。
2004年に発表された医学雑誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン」では、47,150人を対象に12年間調査した結果、低脂肪乳製品を毎日コップ1杯以上飲んだ人は、痛風の発症リスクが少ないことが分かりました。
<もずくなどに含まれるフコダイン>
もずくやわかめなどのぬめり成分であるフコダインは、酸性尿をアルカリ性にする作用があります。
アルカリ性の尿にすることで尿酸をうまく排泄できるようになるので痛風予防に効果が期待できるでしょう。
クエン酸と一緒に摂取することで尿酸に対して相乗効果が期待できます。
またフコダインには中性脂肪を低下させる作用もあるため、肥満を防止し、腎臓の働きが悪くなるのを防ぎます。
<レモン、梅干しなどに含まれるクエン酸>
梅干しやハイビスカスなどに多く含まれるクエン酸は、尿を酸性からアルカリ性にする作用があります。
アルカリ性の尿にすることで、尿酸をうまく排泄できるようになるため、尿酸値の上昇を予防できます。
<魚、鶏肉に含まれるアンセリン>
マグロやカツオ、鳥の筋肉に多く含まれるアンセリンは疲労回復効果が注目されている成分です。
このアンセリンは血糖値の上昇を抑えて、血圧を降下させる作用があることが有名ですね。
さらにアンセリンには尿酸値を下げる効果もあり。
尿酸が増えるのを抑制し、増加しすぎた尿酸を排泄する働きが報告されています。
<青魚に多く含まれるDHA、EPA>
青魚の脂に多く含まれるDHA、EPAは、オメガ3系脂肪酸です。
このDHA、EPAには血液の粘性を低くする作用があり、中性脂肪を低下させます。
中性脂肪を下げることで、血流を改善し、腎臓機能を助けて、尿酸排泄をスムーズにすることができるのです。
ちなみにDHAとEPAでは、EPAの方が中性脂肪を下げる働きが高いです。
<野菜や果物に多く含まれるビタミンC>
ビタミンCは1日1,000㎎以上摂取すると、尿酸排泄や尿酸生成を抑制する効果があることが分かっています。
<食物繊維>
緑黄色野菜や海藻類などに多く含まれる食物繊維には、尿酸の排出を促す作用があります。
【痛風予防におすすめのサプリはある?】
当店で取り扱うサプリの中で、痛風予防におすすめの商品をいくつかご紹介していきましょう。
<ヘルスライフ シーププラセンタ(羊由来エキス)>
当店一番人気のヘルスライフ社のシーププラセンタ。
万能なサプリともいえるプラセンタは痛風予防にも効果的です。
実はプラセンタにはプリン体が含まれています。
そのため痛風予防には向いていないだろう…と考えてしまいがちです。
しかし、近年の研究結果でプラセンタには尿酸の生成を抑制する作用があることが分かってきています。
尿酸はプリン体があればすぐに生成されるというわけではありません。
プリン体に活性酸素が働きかけることによって尿酸が合成されるのです。
つまり体内の活性酸素を減らすことができれば、プリン体が体内にあっても尿酸は合成されません。
プラセンタには活性酸素の働きを抑制する成分(活性ペプチドやビタミンC、ビタミンEなど)が多く含まれているため、体内の活性酸素を除去できます。
プラセンタの抗酸化作用によってプリン体から尿酸が生成されにくくなるため、痛風の発症を予防できると言われていますよ。
実際、動物実験ではマウスにプリン体とプラセンタエキスを同時投与した場合、血中尿酸濃度が低下したという研究結果も報告されています。
<ヘルスライフ スーパーアトランティック フィッシュオイル>
ヘルスライフ社のスーパーアトランティック フィッシュオイルは、魚に豊富に含まれるDHAとEPAをたっぷり含有。
先ほどお話した通り、DHA、EPAには血液の粘性を低くする作用があり、中性脂肪を低下させます。
中性脂肪を下げることで、血流を改善し、腎臓機能を助けて、尿酸排泄をスムーズにすることができるのです。
<ヘルスライフ プロポリス>
プロポリスは、痛風の症状改善や、予防に最適なサプリと言われています。
プロポリスには様々な作用があり、痛風に有効な作用といえば、抗炎症作用、鎮痛作用、細胞賦活作用などがあります。
プロポリスの痛風に有効な作用をまとめてみましょう。
・抗炎症作用
痛風は発作が起こると激しい痛みが起こります。
プロポリスには抗炎症作用があり、痛風の激しい炎症作用を抑えることができるでしょう。
プロポリスは炎症物質の生成を抑制させることで炎症を食い止めます。
またプロポリスに含まれるアントシアニンには、尿酸値を下げる作用と、関節の炎症を緩和する作用があるため、痛風の炎症を鎮静化できるのです。
・鎮痛作用
痛風の激しい痛みは、免疫細胞である白血球が尿酸塩結晶を異物としてみなして、取り囲んで攻撃する際に発生するプロスタグランジンによって引き起こされます。
プロポリスに含まれるフラボノイドは、痛み成分であるプロスタグランジンの生成を妨げる作用があるため、痛みを抑えることができるでしょう。
プロポリスの鎮痛作用はモルヒネの6~7倍も高いと言われており、痛風の激痛を緩和させる成分として非常に有効ですよ。
ただプロポリスには即効性がないため、日常的に継続服用しておくことが必要です。
・尿酸の排出能力を維持・上昇させる
体内で増えてしまった尿酸を排出するためには、腎臓機能を正常に保つ必要があります。
腎臓は血中の老廃物や毒素をろ過する役割があり、腎臓機能を維持するためには、血中の老廃物や毒素を減らすことが重要です。
プロポリスには血中の老廃物や毒素を減らす作用があるため、腎臓の負担を減らすことができますよ。
・腸内環境改善作用&老廃物を速やかに排出する
血中に老廃物や毒素が増えてしまう原因の1つが便秘。
腸に老廃物や毒素がたまると、腎臓には大きな負担がかかってしまいます。
プロポリスには抗菌殺菌作用があるため、腸の機能を悪化させる悪玉菌を減らして、善玉菌が活発化しやすい環境を作る作用があります。
この腸内環境改善作用によって便秘は解消され、老廃物は毒素を排出する前に排出されるようになるでしょう。
そうすれば、腎臓の負担が軽減されるため、腎機能の維持・向上につながり、尿酸排出量が低下するのを防ぐことができます。
・細胞賦活作用による腎臓の活性化
プロポリスの抗菌殺菌作用によって腸内環境が改善されると栄養の吸収効率がアップします。
そうすることで細胞や内臓は必要な栄養素を十分に補給できるようになるので、細胞賦活作用が期待できるのです。
活性化された細胞は、腎臓の働きもよくしてくれるので、尿酸の排出がスムーズになり、痛風予防につながります。
・肥満解消
プロポリスは細胞賦活作用によって、新陳代謝を活性化させて、基礎代謝量をアップさせます。
さらにフラボノイドの脂質吸収抑制作用によって、痩せやすい体質へと改善してくれるのです。
このようにプロポリスには痛風の痛み緩和や、痛風予防におすすめの作用がたくさんあるのです。
特にプロポリスに含まれるフラボノイドの「ケルセチン」は痛風に効果的。
血流改善やコレステロール値を下げる作用、さらには抗炎症作用によって痛風の痛みを緩和する効果が期待できます。
またケルセチンはビタミンCと同時摂取することで尿酸値を下げるという研究結果も報告されています。
ビタミンCは1日2,000~4,000mg以上の摂取で尿酸排出量が増えることが分かっています。
プロポリスサプリとビタミンCは同時に摂取することで相乗的に痛風予防につながるでしょう。
<グッドヘルス マルチビタミン>
グッドヘルス社のマルチビタミンは、バランスの取れたビタミンサプリメントです。
ビタミンBを主体として、ビタミンD、カルシウム、葉酸、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛など痛風予防におすすめのビタミン、ミネラルをたっぷりと配合してます。
痛風に効果のあるビタミン、ミネラルをまとめてみましょう。
・ビタミンB群
ビタミンB群はエネルギー代謝に必要な酵素を助ける補酵素としての役割があります。
特にビタミンB1、B2、B6は三大栄養素をそれぞれ代謝するため、消費エネルギーを増やして肥満を防ぐには大切な栄養成分です。
肥満を解消することで痛風予防につながります。
・葉酸
葉酸は尿酸の濃度を示す血清尿酸値の上昇を抑えたという研究結果が報告されています。
直接的に尿酸値を減らすことができるため、痛風予防に有効です。
・ビタミンE
若返りのビタミンと呼ばれるビタミンEは、抗酸化作用が強いビタミンとして知られています。
抗酸化作用は血行を促進する作用があるため、痛風に有効です。
また、ビタミンEには必須脂肪酸を安定させる作用もあり。
必須脂肪酸は血行促進効果、抗炎症効果、ストレス軽減作用などが期待できるので痛風予防には欠かせません。
・亜鉛
亜鉛は代謝にかかわる栄養素の1つ。
亜鉛が不足してしまうと代謝がスムーズに行われません。
亜鉛が十分にあれば、新陳代謝が活性化され、基礎代謝量もアップするので肥満解消につながります。
また亜鉛には、細胞分裂を促進する作用もあるため、炎症によって傷ついた細胞を修復する作用も期待できます。
【まとめ】
痛風は食生活など生活習慣を改善することで予防できる病気です。
また痛風になると高脂血症や高血圧など他の生活習慣病も併発しやすくなるので、気を付けなければいけません。
生活習慣を改善して、痛風予防に努めましょう。
またその際にサプリメントを取り入れることで無理なく予防対策ができますよ。
<参考商品>