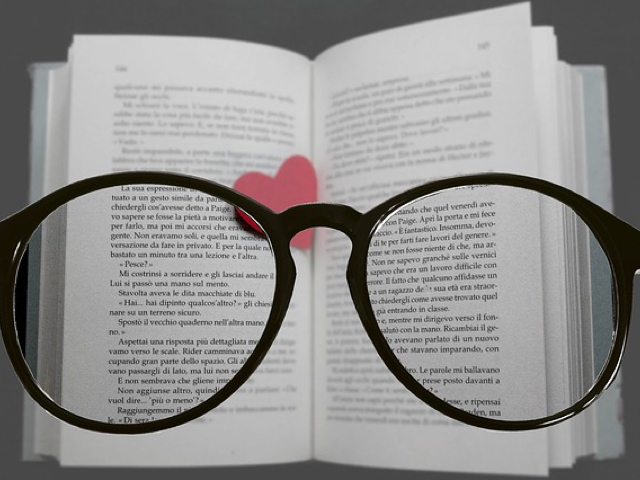五月病対策の鍵は腸と“ストレス”が握っている!実は恐ろしいストレス性疾患とは?
2019年4月26日
プロポリスの抗がん作用と匂い・味について
2019年5月2日年齢を重ねると「あれ何だったっけ?」ということが徐々に増えてきます。
40代や50代だと“ただの物忘れ”と思いがちですが、60歳を過ぎたら“認知症”の可能性も視野に入れなくてはなりません。
というのも超高齢化社会が進む現代日本において高齢者の認知症が様々な社会問題を引き起こしているためです。
認知症は一度発症すると治療によって進行スピードを緩めることはできるものの、完治は難しいとされており、いかに発症を予防するかが老後の健康リスクケアにおいて重要と考えられています。
そこで今回は誰しも発症する可能性がある身近な“認知症”について、発症原因や主な症状、予防方法、さらに今すぐ簡単手軽にリスクケアを始めたい方におすすめの《フィッシュオイルサプリ》について詳しくご紹介します。
目次
◆身近な病気“認知症”とは
年齢を重ねると若い頃と比べて誰しも体の衰えを実感しますが、その中でも脳の衰えとして“もの忘れ”が少しずつ酷くなっていく場合があります。
一昔前だと「老人ボケ」と呼ばれることが多かったこの症状、現在では「認知症」という言葉がすっかり定着しました。
◇“認知症”と“もの忘れ”は全くの別物!
そもそも認知症とは病気の名前ではなく、脳の神経細胞が破壊されて認知機能が衰えることで引き起こされる様々な症状や状態をさす言葉です。
認知症を発症すると少しずつ症状が進行し、徐々に記憶力や判断力、理解力といった認知力が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになります。
一方、もの忘れは単純に脳の老化が原因です。
認知症の場合、体験したことそのものを忘れヒントを与えられても思い出せませんが、もの忘れの場合は体験したことの一部のみを忘れヒントを与えられると思い出すことができるため、認知症は“忘れたこと”に対し自覚がありませんが、もの忘れは“自分は忘れっぽい”と自覚しているという違いがあります。
またもの忘れの場合は症状があまり進行しないため記憶力や判断力、理解力といった認知力が低下することはなく、認知症のように日常生活や社会生活に支障をきたすこともありません。
◇5人に1人が認知症の超高齢化社会がやって来る!
近年超高齢化が進む日本において認知症の患者数も年々増加傾向にあります。
2015年に厚生労働省が発表したデータによると、日本国内の認知症患者数は2012年時点で約462万人もおり、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症を発症しているとのことでした。
また認知症の前段階である「軽度認知障害(MCI:mild cognitive impairment)」を患っている高齢者数は約400万人と推計されており、認知症の患者数と合わせると高齢者の約4人に1人が認知症または予備軍であると報告されました。
厚生労働省の推計によると今後さらに超高齢化が進むと“団塊の世代”が75歳以上となる2025年には国内の認知症患者数は700万人前後まで増加し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を発症すると見込まれています。
◇高齢者だけじゃない!40代・50代の働き盛りも要注意
認知症は基本的に65歳以上の高齢者が発症しますが、65歳未満で発症する場合を「若年性認知症」といいます。
特に40代や50代の働き盛りで発症すると進行が速く症状も重くなる傾向があり、仕事や家庭、子育てや金銭問題など高齢者とはまた違ったサポートが必要となります。
◆認知症の主な種類・原因・症状・対処法について
認知症にはいくつか種類があり、それぞれ原因や症状、対処法が異なります。
ここでは数ある認知症の中でも大多数を占める「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「血管性認知症」の3つについて詳しくご紹介します。
◇アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は日本人が発症する認知症の中で最も患者数が多く、全体の約50%を占めています。
一般的にもの忘れから始まり、新しいことを記憶できない、場所や時間がわからなくなるなど、これまで日常生活において問題なく行えたことが徐々にできなくなっていきます。
◎原因
脳内に異常なタンパク質が蓄積することで神経細胞が死亡し、記憶を司る「海馬」という部分が委縮し、やがて脳全体が委縮していきます。
◎症状
・認知機能障害…新たな経験を記憶できず直ぐ忘れる、日付・日時・場所・家族の顔などが分からなくなる、理解力や判断力が低下して買い物時のおつりの計算や料理ができなくなります。
・行動、心理症状…進行するにつれて妄想、無為・無関心、抑うつ、徘徊、興奮、暴力などの症状が現れます。
◎家族の対処法
・本人の話を否定しないこと…妄想話であっても本人にとっては現実であるため、否定せずによく聞いてあげましょう。
・本人の話に合わせること…同じことを繰り返し言う場合、毎回初めて聞くように話を併せましょう。
◇レビー小体型認知症
レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症に次いで2番目に多い認知症で、全体の約20%を占めています。
就寝中に怒鳴る・奇声をあげる、いないはずの人が見えるといった症状を始め、手足の震えや小刻みに歩くといったパーキンソン病のような症状が現れる場合があります。
また症状の度合いは変動的で、頭がハッキリしている日もあればボーッとする日もあります。
◎原因
「レビー小体」という異常なタンパク質の塊が脳の神経細胞の中に発生し、大脳に広く現れることで発症します。
アルツハイマー型認知症とは違い、脳の萎縮が見られないことが多いという特徴があります。
◎症状
・認知機能障害…注意力の低下、物が歪んで見えるといった症状が現れ、初期段階だと記憶障害が目立たない場合もあります。
・認知機能の変動…日や時間帯によって頭がハッキリしていたり、逆にボーッとしていたりと状態の入れ替わりが起きます。
・幻視…実際には見えないものがハッキリ見える状態。人形を本物の女の子に見間違うといった「錯視」も現れます。
・睡眠時の異常言動…就寝中に大声で叫ぶ、怒鳴る、奇声をあげる、暴れるといった異常言動が現れる場合があります。
・抑うつ症状…気分が沈む、悲しくなる、意欲が低下するといった抑うつ症状はレビー小体型認知症患者の約50%に現れます。
・パーキンソン症状…筋肉のこわばり、小刻みに歩く、無表情、動作が遅い、倒れやすいなどの症状が現れます。
・自律神経症状…倦怠感、立ちくらみ、異常な発汗・寝汗、頻尿、便秘などの症状が現れます。
◎家族の対処法
・転倒に注意…パーキンソン症状に対応するために家の中を片付けて転倒を予防する、手すりを設置するなどしましょう。
・誤嚥に注意…悪化すると嚥下機能が低下し食べ物が気管に入りやすくなるため調理法を工夫する、食事の際は側で見守るなどしましょう。
◇血管性認知症
血管性認知症は国内の認知症患者の約15%を占めています。
脳の損傷によって引き起こされる認知症で、損傷部位や度合いによって症状が異なります。
◎原因
脳梗塞や脳出血による脳血管の障害により周辺の神経細胞が損傷を受けることで発症します。
脳梗塞や脳出血の後に急激に発症する場合が多いです。
◎症状
・認知機能障害…記憶力や判断力は比較的保たれますが、障害が現れる能力とそうでない能力の差がハッキリ現れます。
・行動、心理症状…突然落ち込む、意欲喪失、感情の起伏が激しくなる、些細なことで興奮するといった症状が現れます。
・身体症状…手足の麻痺や感覚障害といった神経症状、言語障害など脳の損傷部位によって異なる症状が現れます。
◎家族の対処法
・規則正しい生活習慣をサポート…意欲低下により日中の活動が少なくなると昼夜逆転や不眠を招くため、それまでの規則正しい生活習慣を崩さないようにデイケアサービスやリハビリテーションなどのサポートを行いましょう。
◆認知症のリスクチェック
認知症は一度発症すると完治が難しく、治療によって進行スピードを緩やかにすることしかできないため発症そのものを予防することが重要ですが、発症した場合はできるだけ初期段階で発見し早期に治療に取り掛かることが重要です。
そこでここでは認知症の初期段階に現れやすい症状をご紹介します。
◎もの忘れがひどくなる
・何度も同じことを言ったり問うたりする
・切ったばかりの電話相手の名前を忘れる
・ものをしまい忘れたり置き忘れたりすることが増え、いつもものを探している
・自分で失くしたものを人に盗まれたと言う
◎場所や日時が分からなくなる
・歩き慣れたはずの道で迷ってしまう
・約束の日時や場所を間違える
◎理解力や判断力が低下する
・テレビを見ても内容が理解できなくなってきた
・新しいことを覚えられなくなってきた
・話のつじつまが合わなくなってきた
・買い物時のおつり計算や料理、片付け、車の運転などでミスが多くなってきた
◎意欲低下
・好きだったテレビ番組や趣味に対し興味を失った
・何をするのも億劫で塞ぎ込みがち
・下着を替えないなど身だしなみに気を使わなくなる
◎精神的に不安定になる
・「自分は頭がおかしくなった」と本人が訴える
・一人になることを寂しがったり怖がったりする
・外出時に何度も持ち物を確認する
◎人柄が変わる
・自分の失敗を人のせいにする
・周囲から「最近様子がおかしい、人が変わった」と言われる
・頑固になった
・些細なことで怒りやすくなった
◆認知症と社会問題について
認知症を発症すると基本的に医薬品を服用する「薬物療法」か、患者が興味を持つことを活かし快適な環境づくりを行い脳に刺激を与える「非薬物療法」のどちらかを行います。
しかし認知症患者の治療は本人だけでなく家族への負担が非常に大きく、近年では認知症患者本人と家族によるトラブルが社会問題化しています。
◇認知症患者の徘徊・行方不明者数の増加
認知症患者の中には、外出後に自宅に戻れなくなり警察に保護されるケースがあります。
その場合、多くは直ぐに身元が判明し自宅に戻ることができますが、中には事故に遭い亡くなるケースもあります。
さらに認知機能の低下により自分の名前や自宅住所、関係者の連絡先が言えず行方不明者として施設や医療機関に収容されるケースもあります。
◇ゴミ屋敷・孤独死の増加
近年、自宅の庭やベランダ、室内などに大量のゴミが溜まり、悪臭や害虫による近隣への被害が社会問題として取り上げられるケースが増加していますが、原因となっている住人の中に認知症患者が多いという特徴があります。
これは認知機能の低下による「セルフネグレクト(自己放任)」と呼ばれ、平成22年の調査では全国に約1万人いると推計されています。
また家族や地域から孤立したがゆえに自宅で誰にも看取られることなく亡くなり長期間放置される「孤独死」のケースも増加しています。
◇消費者被害
高齢者の消費者トラブルは年々増加傾向にありますが、認知症患者の場合は特に被害件数が多いとされています。
認知症患者は判断力が低下しているため、悪質な訪問販売などへの対応が上手くいかないケースが多いためです。
実際に平成25年度には認知症患者の消費者被害件数が約1万1,500件と報告されています。
◇車の運転事故
近年、高齢者ドライバーによる交通トラブルや事故の報告件数が急増しています。
認知症患者は道に迷いやすいほか、判断力や理解力が低下するため高速道路や一般通行エリアを逆走する、アクセルとブレーキを踏み間違えてしまった結果大きな事故を引き起こしてしまうといったケースが増加しています。
◇高齢者虐待・介護殺人
認知症患者が高齢である場合、家族や介護者が患者の問題行動に振り回されて身体的・肉体的ストレスが溜まり、患者本人を虐待してしまうケースが年々増加しています。
また高齢者夫婦のどちらかが認知症を患いどちらかが介護を行う「老々介護」や、周りのサポートを受けられず家族だけで先の見えない介護を続けた結果、患者本人を殺害または無理心中を図るケースが年々増加しており、近年では毎年20件以上報告されています。
このように家族の誰か、特に高齢者が認知症を発症すると患者本人だけでなく家族やその周囲、さらには社会までも様々な問題に直面することになるため、認知症そのものをいかに予防するかが重要視されています。
◆認知症の予防方法
日本国内において認知症の約50%を占めるアルツハイマー型認知症の場合、発症原因の50%が生活習慣にあるとされており、アルツハイマー型認知症患者の約30%は生活習慣を改善することで発症を予防できるとされています。
血管性認知症の発症原因の一つである脳梗塞も生活習慣が大きく関係しているため、同じく生活習慣を改善することで発症の予防が期待できます。
ここでは認知症予防に効果的な生活習慣の改善ポイントをご紹介します。
◇食生活
◎タンパク質を積極的に摂取!栄養バランスも重要!
一般的に食事量は加齢と共に少なくなりますが、肉や魚などタンパク質を豊富に含む食材の摂取量が減少すると体が低タンパク状態となり認知症リスクがアップします。
また食事内容の栄養バランスが偏っていると低栄養状態となり、こちらも認知症リスクがアップします。
そのため食事量に関わらず肉や魚、野菜などをバランスよく摂取することを心掛けましょう。
◎塩分控えめ&低糖質を心掛けること!
塩分が多く含まれる食事ばかりだと高血圧を引き起こし、高血圧は動脈硬化を引き起こして脳梗塞などが原因となる血管性認知症のリスクがアップします。
また糖質の摂取量が多いと糖尿病の原因となりますが、糖尿病はアルツハイマー型認知症や血管性認知症の発症原因にもなるため、低糖質の食事を心がけるようにしましょう。
◇運動
体を自由に動かすことができるのは脳が正常に機能しているからとも言え、運動を行うことで逆に脳を刺激して活性化させることもできます。
実際に運動を行うことでアルツハイマー型認知症の発症リスクを最大65%も下げることができるという報告もあります。
また運動は脳を活性化させるだけでなく、全身の血流を促したり筋量を維持したりと健康な生活を送るうえでも欠かせません。
日頃から運動をしっかり行っていると認知症を発症した場合の急激な進行を予防することができるほか、認知症の発症前に体で覚えた動きは失われにくいともいわれています。
運動は激しいものではなく、散歩やウォーキング、体操やヨガを毎日の習慣にすることが重要です。
◇頭を使って達成感を味わおう!
認知症予防に運動が効果的ですが、さらに知的作業を組み合わせることで予防効果がアップします。
例えば散歩やウォーキングの時に俳句や短歌を作りながら、ガイドブック片手に知らない街をブラブラ、目に付いた植物の名前を思い出しながら、など作品や記録に残しながら毎日続けることで脳が刺激され、作品や記録が目に見える形である程度の数が仕上がることで達成感が味わえ、さらに脳を刺激することができます。
◇他人とのコミュニケーションを積極的に!
人は他人とコミュニケーションをとることで脳が刺激されます。
上記で紹介した運動や頭を使う作業などを他人と一緒に行えば認知症予防効果もさらにアップします。
特に60代になり仕事の定年を迎えると、社会との繋がりがそれまでと比べて希薄になりがちです。
趣味仲間や地域のサークルなどに積極的に参加して様々な人とコミュニケーションを取る、家族と積極的に会話するといったことが重要です。
◆今すぐ認知症予防を始めるなら簡単手軽な《フィッシュオイルサプリ》がおすすめ
認知症は一般的に65歳以上の発症率が高いため、40〜50代で認知症予防のためにケアをしているという方は意外と少ないです。
しかし認知機能の衰えは40代から始まっており、40〜50代でどれだけケアできるかが老後の発症リスクを大きく左右します。
とはいえ働き盛りの40〜50代といえば認知症よりも糖尿病や高血圧、動脈硬化やメタボリックシンドロームなといった生活習慣病のケアのほうが気になりますよね。
そこでおすすめしたいのが《フィッシュオイルサプリ》です!
フィッシュオイルサプリなら認知症予防と健康ケアの両方を一度に行うことができます。
◇フィッシュオイルサプリの健康パワーとは
フィッシュオイルサプリとは青魚などに豊富に含まれる“フィッシュオイル(魚油)”を主成分としたサプリメントです。
フィッシュオイルそのものは“体に良い油”といわれるω-3系脂肪酸(オメガ3)に分類され、中性脂肪値やコレステロール値を下げる作用に優れたEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)なども豊富に含まれています。
このEPAとDHAには糖尿病や高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、メタボリックシンドロームといった生活習慣病の改善・予防効果に優れていることから近年では健康系サプリに欠かせない成分となっていますが、DHAにはさらに脳機能を高める作用もあります。
DHAは体内で生成できない脂肪酸であるため主に青魚から摂取する必要があり、摂取したDHAのほとんどは脳の記憶学習機能を司る「海馬」に存在し、神経細胞間の情報伝達がスムーズにいくようサポートする働きがあります。
特に記憶学習機能をサポートする作用に優れているため、DHAを積極的に摂取することで記憶力や集中力、判断力、情報処理能力を向上させることができます。
認知症の中でもアルツハイマー型認知症は脳の海馬のDHA量が半減しているため、DHAはアルツハイマー型認知症の予防において高い効果を発揮すると考えられています。
つまりEPAやDHAを豊富に含むフィッシュオイルサプリを摂取すれば面倒な食事制限や運動をしなくても生活習慣病や認知症の予防ケアができるということです。
◇ブリリアントライフの高品質なフィッシュオイルサプリ
ブリリアントライフでは今現在の健康状態が気になるという40〜50代の方をはじめ、老後の認知症リスクが怖いという40〜50代の方、今からでも認知症予防を始めたいという60代以上の方におすすめのフィッシュオイルサプリを豊富なラインナップでご用意しております。
◎ヘルスライフ スーパー アトランティック フィッシュオイル ( オメガ3 ) 100粒
配合成分 ⇒ フィッシュオイル:1,000mg、EPA:310mg、DHA:210mg、ビタミンE:1mg
◎グッドヘルス オメガ3 フィッシュオイル 1000mg 150粒
配合成分 ⇒ フィッシュオイル:1,000mg、EPA:180mg、DHA:120mg
◎グッドヘルス オメガ3 フィッシュオイル 1500mg 200粒
配合成分 ⇒ フィッシュオイル:1,500mg、EPA:270mg、DHA:180mg
◎グッドヘルス オメガ3 フィッシュオイル 2000mg 200粒
配合成分 ⇒ フィッシュオイル:1,000mg、天然フィッシュオイル同等成分:2,000mg、EPA:360mg、DHA:240mg
これらの商品はどれも高品質なフィッシュオイルやEPA・DHAをたった1粒でたっぷり摂取することができます。
これなら食生活が乱れている方や青魚が苦手な方でも気軽に続けることができますね。
40代以降になると年齢を重ねる毎に健康面での不安が増していくもの・・・。
健康トラブルが現れる度にケアする方法も間違いではありませんが、これから超高齢化社会を迎える日本においてあらゆる健康リスクを考え早いうちから健康ケアを始めるに越したことはありません。
「いつまでも健康で若々しさを維持したい!」という方は、今すぐにでも始められる老後のリスクケアとしてフィッシュオイルサプリをお試し下さい。