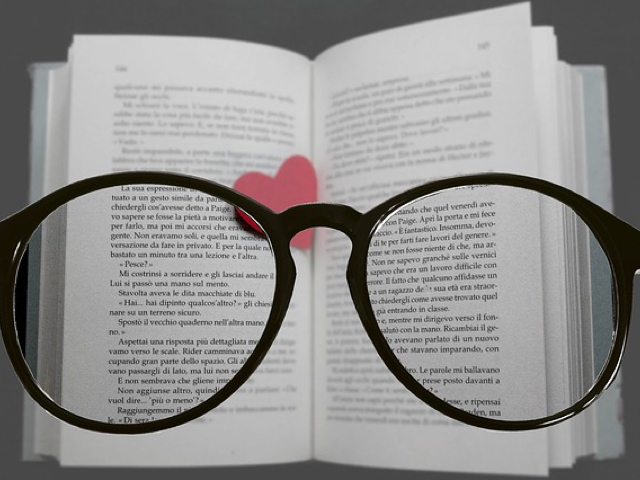目の2大疾病といえば白内障と緑内障!白内障と緑内障は名前は似ているけど全く別の病気!
2020年11月17日
メタボリックシンドロームは肥満だけではない!どのような状態をメタボリックシンドロームと呼ぶの?予防方法はある?
2020年11月23日
脂質異常症は誰にでも起こりうる生活習慣病の1つです。
日本において、脂質異常症の総患者数は220万人を超えており、その患者数は年々増加しているとも言われています。
ここでは脂質異常症とはどういう病気なのか?その原因は何なのか?予防方法はあるのか?など詳しくまとめてみましょう。
目次
【脂質異常症とは?】
脂質異常症とは血液中の中性脂肪(トリグリセライド)やLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が基準値よりも高い、またはHDLコレステロール(善玉コレステロール)が基準よりも低い状態のことを言います。
血液中に余分な脂質が多くなると、血液がドロドロの状態になり、動脈硬化を起こしやすくなります。
動脈硬化が起こると心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高くなり、命に関わる重大な疾病につながる恐れがあるのです。
血液中には脂質としてコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類があります。
コレステロールは、人の細胞膜や胆汁酸(消化吸収に必要)、ホルモンの原料となる重要な成分です。
また、中性脂肪は体内での貯蔵用エネルギーとなる他、保温作用や、外部からの衝撃を和らげたり、内臓を固定したりするなど、体内で重要な役割を果たしています。
ただこれらの脂質は多すぎたり、少なすぎたりすると問題が起こり、脂質異常症になるのです。
近年、私達日本人のライフスタイルは欧米化が進み、脂質異常症と診断される患者さんが増えています。
それに伴い、動脈硬化症患者さんも増えているのです。
脂質異常症はそれだけでは特に症状はないものの、体中の血管で静かに動脈硬化が起こり始めます。
動脈硬化が進行していくと全身の動脈は硬くなり、血管の内側は狭くなるため、血液の流れが滞ってしまうのです。
血液の流れが悪くなると、血管が詰まりやすくなり、心臓の血管が詰まれば急性心筋梗塞を起こしますし、脳の血管が詰まれば脳梗塞を引き起こしてしまうでしょう。
【脂質異常症と高脂血症は違うの?】
高脂血症という病名を聞いたことがある人は多いでしょう。
実は脂質異常症は以前「高脂血症」と呼ばれていました。
「高脂血症」という名前では、脂質が多い時だけが悪いというイメージになってしまいます。
しかし、善玉コレステロールが基準値よりも少なすぎても、悪玉コレステロールが基準よりも多い時と同じように危険であるため、「脂質異常症」という名前で呼ばれるようになりました。
つまり脂質異常症と高脂血症は名前の呼び方が違うだけで病気としては同じものです。
脂質異常症は
(1)悪玉コレステロール値が高い
(2)中性脂肪値が高い
(3)善玉コレステロール値が低い
の3つをまとめて、その病名がついています。
どれか1つでも当てはまれば脂質異常症と診断されます。
ちなみに脂質異常症の目安は
・中性脂肪(トリグリセライド) 150mg/dl以上
・善玉(HDL)コレステロール 40㎎/dl以下
・悪玉(LDL)コレステロール 140㎎/dl以上
となっています。
【血液中に存在する脂質とは?】
血液中に存在する脂質には
・コレステロール
・中性脂肪
・リン脂質
・遊離脂肪酸
があります。
その中でもメインとなるのが「コレステロール」と「中性脂肪」です。
通常、血中脂質は一定の量に保たれるように調節されています。
ここではコレステロールと中性脂肪についてまとめてみましょう。
<コレステロール>
コレステロールは、細胞膜を構成する成分であり、各種ホルモンや消化吸収に必要な胆汁酸の原料ともなります。
また、コレステロールは悪玉(LDL)コレステロールと善玉(HDL)コレステロールの2種類が存在します。
悪玉コレステロールは、肝臓で作られたコレステロールを体の隅々まで運ぶ働きをしていて、善玉コレステロールは使い切れず余ったコレステロールを回収して肝臓に戻す働きをしているのです。
つまり、血液中に悪玉(LDL)コレステロールが増えすぎてしまうと血管の壁にコレステロールが溜まり、動脈硬化を進行させる要因となります。
一方、血液中に善玉(HDL)コレステロールが増加すると、血管内にコレステロールは蓄積しにくくなるため、動脈硬化の進行を予防できるでしょう。
・悪玉(LDL)コレステロールの中でも最も悪い「超悪玉コレステロール」
脂質異常症の大きな要因となる悪玉(LDL)コレステロールには「超悪玉コレステロール」と呼ばれるものもあります。
悪玉コレステロールを調べてみると、心筋梗塞などの心疾患を起こした患者さんは小型の悪玉コレステロールが多くみられることが分かってきました。
小型の悪玉(LDL)コレステロールは、小さいため血管壁に侵入しやすく、肝臓に吸収されにくいため血液中に長くとどまります。
すると徐々に酸化されて、動脈硬化の直接的な原因となってしまうのです。悪玉(LDL)コレステロールが多い人の中でも、特に超悪玉(小型LDL)コレステロールの量が多いほど、心筋梗塞を起こすリスクは高まるでしょう。
なぜ悪玉コレステロールが小型化してしまうか?は解明されていないものの、善玉(HDL)コレステロールが少ない人、中性脂肪値や血糖値、血圧が高い人や、肥満の人、狭心症や心筋梗塞を以前に起こしたことがある人は、超悪玉コレステロールが多い傾向にあるため気をつけなければなりません。
<中性脂肪>
中性脂肪は脂肪組織に蓄えられてエネルギー貯蔵庫として働くほか、皮下脂肪となって体温の保持、衝撃から体を守るクッションの役目を果たします。
また内臓を固定する役割もありますよ。
中性脂肪は活動エネルギー源の1つで非常に重要ですが、悪玉(LDL)コレステロールと同じように、体内で過剰に増えてしまうと、血管の健康を損なってしまうのです。
また中性脂肪は皮下や内臓周辺に貯蔵されるため、必要以上に増えてしまうと肥満を招きます。
特に内臓周辺に中性脂肪が増えると、生活習慣病の大きな原因となる「内臓脂肪型肥満」を引き起こしてしまうでしょう。
この中性脂肪は、アルコール類、甘いもの(糖分系)で増えやすい傾向があるため、お酒をよく飲む人や、ケーキやクッキーなど甘いものを翌食べる人は、中性脂肪が増えやすいため注意が必要です。
【脂質異常症の種類】
脂質異常症は血液中に多く(もしくは少なく)なる脂質の種類によって
・高LDLコレステロール血症(悪玉(LDL)コレステロールが多いタイプ)
・低HDLコレステロール血症(善玉(HDL)コレステロールが少ないタイプ)
・高トリグリセライド血症(中性脂肪(トリグリセライド)が多いタイプ)
の3つに分類することができます。
それぞれの特徴をまとめてみましょう。
<高LDLコレステロール血症>
悪玉(LDL)コレステロールが多い状態のこと。
脂質異常症の中ではこのタイプが最も多く見られます。
脂質異常症かどうかを判断する上で、悪玉(LDL)コレステロール値は重要な指標であり、定期的な検査が必要です。
<低HDLコレステロール血症>
善玉(HDL)コレステロールが少なすぎる状態のこと。
善玉コレステロールが少ないと、血液中に余っているコレステロールをうまく回収することができなくなるため、コレステロールが溜まりやすい状態になります。
それによって動脈硬化のリスクが高まってしまうでしょう。
脂質異常症=コレステロールが高いというイメージが強いですが、実は善玉コレステロールの少なさも問題となるため、善玉コレステロールの数値もしっかりとチェックしておかなければなりません。
<高トリグリセライド血症>
高トリグリセライド血症は中性脂肪が多すぎる状態のこと。
中高年の男性にはこのタイプが多くみられます。
また中性脂肪が多くなると、悪玉(LDL)コレステロールも増えやすくなることが研究結果から明らかになっています。
また脂質異常症は原因によって他の病気を伴わずに起こる「原発性」と他の病気に伴って起こる「続発性」の分類することもできます。
<原発性脂質異常症>
原発性脂質異常症は生活習慣の乱れ、家族性高コレステロール血症のように遺伝的な要因で起こるものがあります。
<続発性脂質異常症>
続発性脂質異常症とは、
・甲状腺機能低下症や副腎皮質ホルモン分泌異常などのホルモン分泌異常
・糖尿病や腎臓病などの他の疾患
・副腎皮質ステロイドホルモン、経口避妊薬などの薬剤
によって起こる脂質異常症のことです。
【脂質異常症の症状とは?】
脂質異常症は多くの場合、症状が現れることがありません。
健康診断を受けて検査値が悪いことで発覚するケースがほとんどなのです。
そのため、気が付かないうちに動脈硬化が進行してしまう可能性があります。
脂質異常症からの動脈硬化は「沈黙の病気」と言われていますが、その由来は自覚症状がないからです。
続発性の脂質異常症に関しては、病気の症状がきっかけとなって判明するケースもあります。
【脂質異常症の検査・診断方法とは?】
脂質異常症を調べる検査には、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールがあり、いずれも血液検査によって血液中の総コレステロール値、中性脂肪値、HDLコレステロール値、LDLコレステロール値を測定し、脂質異常症の有無を判断します。
中性脂肪は食後数時間かけて上昇するため、正確な数値を検査するためには午前中に朝食を抜いた状態で採決するのが望ましいとされています。
脂質異常症と判断される基準は
・LDLコレステロールが140㎎/dl以上(高LDLコレステロール血症)
・LDLコレステロールが120~139㎎/dl(境界域高LDLコレステロール血症)
・HDLコレステロールが40㎎/dl未満(低HDLコレステロール血症)
・中性脂肪が150㎎/dl以上(高トリグリセライド血症)
の、いずれかです。
【脂質異常症の原因とは?】
脂質異常症にはいくつかの原因があります。
それぞれまとめてみましょう。
<過食、脂肪の多い食生活>
近年、日本国内で脂質異常症患者さんが増えたのは、食の欧米化が進み動物性脂肪の多い食事が増えたことが背景になると言われています。
脂肪の多い肉、卵や乳脂肪分の多いバターやチーズ、カップラーメンなどインスタント食品の食べ過ぎはコレステロール値が高くする原因の1つです。
食べ過ぎや脂肪の多い食生活は脂質異常症を招いてしまうでしょう。
<過度のアルコール摂取>
中性脂肪があがる要因には、果物や甘いお菓子の食べ過ぎの他、お酒の飲みすぎがあります。
過度のアルコール摂取は高トリグリセライド血症を引き起こしてしまうでしょう。
<運動不足>
運動不足になると、体内で消費されるエネルギー量が減少してしまうため、脂質の代謝が悪化。
結果として脂質が溜まりやすくなり、脂質異常症を引き起こしてしまうでしょう。
近年、脂質異常症は増えたのは車の普及によって慢性的な運動不足の状態にある人が多いためと言われています。
<喫煙>
タバコを吸うと、善玉(HDL)コレステロール値が低くなり、脂質異常の状態になりやすいことが判明しています。
<ストレス>
ストレスを受けた時に分泌されるストレスホルモンには、コレステロールを増やす作用があります。
そのため過度なストレスを受けると、コレステロールが溜まりやすくなり、脂質異常症になるのです。
意識的にストレスがたまらないように工夫しなければなりません。
<病気>
肝臓病、糖尿病、甲状腺機能低下症、腎臓病などの病気が原因で、脂質異常症になる場合があります。
<遺伝>
遺伝的な要因によって起こる脂質異常症は「家族性高コレステロール血症」と呼ばれています。
このタイプは、遺伝性ではない脂質異常症に比べて、悪玉(LDL)コレステロール値が著しく高く、動脈硬化が進行しやすいです。
親、祖父母、兄弟など血縁者に脂質異常症を発症している人がいる、55歳未満(男性の場合)または65歳未満(女性の場合)で心筋梗塞を起こした家族がいるといった場合には、家族性高コレステロール血症になる可能性が高いでしょう。
定期的にLDLコレステロール値を測定し、予防対策を心がけるようにしましょう。
・家族性高コレステロール血症とは?
家族性高コレステロール血症は、若い時からLDLコレステロール値が高く、心臓の血管に動脈硬化を起こす遺伝性の疾患のこと。
軽症のケースで500人に1人以上、重症は100万人に1人以上と言われていて、日本には25万人以上の患者さんがいます。
症状は若いころからLDLコレステロール値が高いこと以外は特にありません。
LDLコレステロールは通常であれば、肝臓で処理されるものの、この疾患では肝臓でうまく処理できないため、血液中に蓄積し、若い人でも動脈硬化を起こし、心筋梗塞、狭心症を発症させてしまうのです。
【動脈硬化を進める危険因子とは?】
脂質異常症が動脈硬化を進行させる危険因子になることを、ここまででお話してきましたね。
その他にも動脈硬化の危険因子はあります。
まとめてみましょう。
<高血圧>
血圧が高いと動脈に強い圧力がかかり続けることになるため、血管の内壁は傷つきやすく、脂質異常症と高血圧が併発すると動脈硬化は進行しやすくなります。
<糖尿病>
血糖値が高い状態が続くと、悪玉(LDL)コレステロールは酸化されたり、小型化されたりして、より血管壁に入りこみやすくなってしまいます。
すると動脈硬化は一層進行することになるでしょう。
<加齢(男性45歳以上、女性閉経後)>
加齢が進むと、血管内も活性酸素によって老化が進むため、動脈硬化が起こりやすくなります。
<喫煙>
喫煙は善玉(HDL)コレステロールを減らしてしまい、悪玉(LDL)コレステロールを酸化させやすくしてしまいます。
喫煙習慣は脂質異常症とともに、動脈硬化を進行させる大きな危険因子となるため、喫煙はできるだけ控えた方がよいでしょう。
動脈硬化は脳、心臓など体中の血管で起こり、様々な疾患を引き起こしてしまいます。
傷つき、弱くなった血管が切れてしまうと脳出血や大動脈瘤を引き起こします。
また血栓が血液に乗って流れ、血管の細い部分で詰まってしまうと狭心症や心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、一過性脳虚血発作、脳梗塞などを引き起こしてしまうのです。
動脈硬化は起こる場所によって命に関わる重大な病気を発症してしまいます。
【脂質異常症の治療方法】
脂質異常症の治療は、年齢、性別、高血圧・糖尿病の有無、喫煙習慣、家族の既往歴などからコレステロールや中性脂肪の目標値を設定して行っていきます。
治療方法は
・食事療法
・運動療法
の2つが基本です。
食事療法と運動療法を行っても、うまく脂質管理の目標値に達成できない場合には、薬物療法が行われます。
また元々持っている危険因子が多く、動脈硬化や動脈硬化による疾病を起こす危険性が高い場合にはすぐに薬物療法が開始されるでしょう。
ここでは食事療法と運動療法、薬物療法についてまとめてみましょう。
<食事療法>
食事療法にはいくつかのポイントがあります。
それぞれまとめてみましょう。
・エネルギーを摂りすぎない
肥満は脂質異常症を招きます。
適正体重に近づけると内臓脂肪を減らすことができますので、エネルギー摂取量を適正にすることが大切です。
1日に必要なエネルギーの目安は、標準体重 [ 身長(m)x 身長(m) ×22 ] × 25~30kcalになっています。
・主食はきちんと食べて、動物性脂肪を控え目に
ごはん、パンなどの主食の穀物類は脂質が少ないため、主食はきちんと食べましょう。
そして肉類などの動物性脂肪は少し控え目にするとよいです。
肉を食べるときは、牛肉よりも鶏肉の方が、脂身は少ないですし、ヒレやささみなど食べる部位を工夫するのがおすすめですよ。
・肉類よりも魚介類(特に青魚)
悪玉(LDL)コレステロールを減らし、善玉(HDL)コレステロールを増やすには、肉類よりも魚類の割合を多めにするように意識しましょう。
魚に含まれているDHAやEPA(不飽和脂肪酸)には、悪玉(LDL)コレステロールを減らす働きがあるため、新鮮な魚は積極的に食べたいですね。
ちなみに焼き魚よりも、刺身や煮魚の方が、EPA、DHAを効率よく摂取することができると言われていますよ。
・大豆類(植物性タンパク質)を摂取しよう
大豆に含まれる植物性タンパク質は、血液中のコレステロールや中性脂肪を減らす働きがあります。
煮豆、豆腐、納豆など大豆製品は毎日の食事に取り入れるようにしましょう。
タンパク質は食事の15~20%は摂取しておきたいです。
・コレステロールを多く含む食品は控え目に
内臓類、卵、肉の脂身などコレステロールを多く含む食品はできるだけ控えるようにします。
コレステロール摂取量は1日300㎎以下にしましょう。
・油を料理は1日2品までにする
天ぷら、揚げ物、炒め物、マヨネーズなどはエネルギーが高いため、油を使った料理は控え目にしましょう。
・食物繊維を毎食食べるようにする
食物繊維はコレステロールを減らすのに役立つ成分の1つで、野菜、果物、豆類、キノコ類、海藻類などに多く含まれています。
野菜、キノコ、海藻類などは毎食2~3品は食べるようにしましょう。
1日25g以上の食物繊維の摂取が理想的です。
・アルコールと甘いものは控えめに
アルコール、お菓子、清涼飲料水、ジュースなど糖分を多く含む食品を食べ過ぎると、中性脂肪を増やしてしまいます。
特に夜寝る前に摂取すると内臓脂肪がつきやすいので注意が必要です。
・アルコールは控え目に
アルコールの過剰摂取は中性脂肪を増やしてしまいます。
アルコールは1日25g以下にしましょう。
具体的にはビール中瓶1本、日本酒180ml、焼酎100ml、ワイン200ml程度です。
・食べ方にも注意が必要
食事を食べる際には、早食い、まとめ食いはしないようにして、よく噛んで食べます。
また外食はできるだけ控えて、薄味にして自炊するようにしましょう。
朝食・昼食・夕食と1日3食きちんと摂取して、和食を多く取り入れるのが効果的。
なるべく腹八分目でやめて、就寝2時間前には食べないようにします。
<運動療法>
運動は動脈硬化予防にもよいとされています。
特にウォーキング、水泳、サイクリング、ジョギング、なわとびなどの有酸素運動がおすすめです。
有酸素運動は15分以上続けると、効率よく脂肪を燃焼することができるので、1回につき15分以上行うのが理想的でしょう。
有酸素運動で得られる効果は以下の通りです。
・中性脂肪が減って、肥満が解消される
・動脈硬化を抑制する善玉(HDL)コレステロールが増える
・筋肉量が増えて基礎代謝が上がり、脂肪を燃焼しやすい体になる
・血圧が下がる(高血圧予防)
・血糖コントロールをしやすくなる(糖尿病予防)
<薬物療法>
生活習慣の改善を行ってもLDLコレステロール値、中性脂肪値が思うように下がらない場合には、薬物治療を開始します。
薬物治療を始めたからと言って、運動療法や食事療法が終わるわけではなく、生活習慣の改善は続けなければ意味がありません。
薬物療法で使用される主な治療薬はこちらです。
・HMG-CoA還元酵素阻害薬
肝臓でのコレステロール産生を抑制し、LDLの受け皿を増やし、血液中の悪玉(LDL)コレステロールを減らしていきます。
・フィブラート系薬剤
肝臓での中性脂肪の産生を抑制し、胆汁へのコレステロール排泄を増加させます。
・陰イオン交換樹脂
胆汁液と陰イオン交換樹脂が結合して、コレステロールの再吸収を抑制。
肝臓や血液中の悪玉(LDL)コレステロールを減少させます。
・ニコチン酸誘導体
中性脂肪の分解の促進と、コレステロール排泄の促進が期待できます。
・プロブコール
コレステロールから胆汁酸合成を促進し、悪玉(LDL)コレステロールの分解を促進します。
・ニコチン酸系
ビタミンの一種であり、肝臓での中性脂肪産生を抑制します。
また善玉(HDL)コレステロール値を上昇させる効果もあります。
・EPA(エイコサペンタ塩酸)
青魚に含まれる不飽和脂肪酸であるEPAから作られた薬剤で、中性脂肪値を下げる作用があります。
また血液をサラサラにしてくれる効果も期待できます。
【脂質異常症におすすめの食材と控えておきたい食材】
脂質異常症では食事療法が非常に重要となってきます。
では脂質異常症の方はどのような食材を選べばよいでしょうか?
ここでは脂質異常症におすすめの食材、摂取を控えておきたい食材をそれぞれまとめてみましょう。
<おすすめ食材>
・レンコン、ブロッコリーなどの野菜、バナナ、リンゴなどの果物
抗酸化作用のあるビタミンC、ビタミンE、βカロチン、ポリフェノール類を豊富に含んでおり、活性酸素を除去してくれます。
・青魚(イワシ、サンマ)サケ、タラ
EPAやDHAなどのオメガ3系脂肪酸は、中性脂肪を減らす働きがあります。
・キノコ、豆類、海藻類
食物繊維を豊富に含んでおり、コレステロールを減らす作用があります。
・オリーブオイル
悪玉(LDL)コレステロールを減らす働きがあります。
<摂取を控えておきたい食材>
・鶏卵の黄身、イクラ・タラコなどの魚卵
コレステロールを多く含んでいるため、食べ過ぎには注意が必要です。
ただ、卵の白身は良質なタンパク質を豊富に含んでいるので積極的に摂取してOK。
・魚の干物
魚の干物は、体内の酸化脂質を増やしてしまうので、動脈硬化につながりやすいです。
・脂身の多い肉の部位、内臓系
脂身の多い肉や内臓は脂質が多く含まれているため、コレステロールが溜まりやすいです。
赤身の多い肉、ささみであれば問題ありません。
・酸化した油
使い古した油や、時間の経過したポテトチップスや揚げ物などには酸化した油が付いています。
この酸化した油は酸化脂質を増やしてしまうのでよくありません。
【脂質異常症の予防方法】
脂質異常症を予防するためには、コレステロールと中性脂肪を増やしすぎないことが大切です。
ではどのように予防すればよいでしょうか?
予防方法をまとめてみましょう。
<コレステロールを減らす予防策>
・禁煙する
タバコは善玉(HDL)コレステロールを減らし、悪玉(LDL)コレステロールの酸化を促進してしまいます。
動脈硬化の直接的な要因となってしまうので、禁煙を心がけましょう。
・ストレスをため込まず、うまく解消する
ストレスを受けた時に分泌されるストレスホルモンは、コレステロールを増やしてしまいます。
ストレスを抱えずに、うまくストレス解消するようにしましょう。
また、睡眠をしっかりと確保することも大切です。
・適度な運動をする
適度な運動は善玉(HDL)コレステロールを増やします。
1日10000歩以上歩く人は1日2000歩未満の人に比べて10%以上も悪玉(HDL)コレステロールが多くなっているんです。
低HDLコレステロール血症の患者さんだけではなく、すべての脂質異常症の予防に適度な運動はおすすめです。
・ビタミン類を摂取する
ビタミンCやビタミンEには、悪玉(LDL)コレステロールの酸化を防いで、動脈硬化を予防する作用があります。
ビタミンは、ニンジン、カボチャ、トマト、ピーマンなどの緑黄色野菜や、レモン、オレンジなどの果物にも多く含まれています。
またサケ、サバなどの魚にもビタミン類は豊富に含まれていますよ。
また、ビタミンCとビタミンEは一緒に摂取することでより効率的に働きます。
・コレステロールが多い食品は日頃から控える
鶏卵(黄身)、うなぎ、イクラ・タラコなどの魚卵はコレステロールが多い食品として有名です。
コレステロールが多い食品を食べると、血中コレステロール値があがってしまう人は特に注意が必要です。
<中性脂肪を減らす予防策>
・アルコールを飲みすぎない
過度なアルコール摂取は、中性脂肪を増やす原因になります。
適量のアルコールであれば、善玉(HDL)コレステロールを増やす作用があるので問題なし。
適量とはビールであれば大瓶1本、日本酒であれば1合、ワインではグラス2杯程度までです。
アルコールはカロリーがありますし、つまみなどで揚げ物などを食べてしまうとカロリーオーバーの原因になってしまうでしょう。
・夜間は食べない
夜間は体を動かさないためエネルギー消費量は少ないです。
そのため食べたものは中性脂肪として蓄えられやすくなります。
夕食のカロリーは控えめにして、寝る前に物を食べないように気を付けましょう。
・腹八分目でやめる
慢性的な食べ過ぎは、エネルギーが余って、中性脂肪として体内にどんどん蓄積されてしまいます。
食べ過ぎは肥満につながるので、食事は腹八分目にしておきましょう。
食べ過ぎを予防するために「ゆっくりと食べる癖をつけること」「一口ごとに30回以上よく噛んで食べる」「食事の途中で箸を置いて休む」などの食べ方を実践するとよいですよ。
・適度な運動をする
中性脂肪は内臓につきやすいです。
内臓脂肪は運動によって減らすことが可能です。
おすすめはウォーキング、アクアサイズ、ジョギング、エアロバイクなどの有酸素運動です。
1回15分以上の有酸素運動を行えば、内臓脂肪を効率よく燃焼することができるでしょう。
1日2~3回、週に3~4日程度続ければ効果的です。
【脂質異常症におすすめのサプリメントは?】
当店で取り扱うサプリメントの中で、脂質異常症の予防におすすめのサプリをご紹介していきましょう。
<ヘルスライフ サメ肝油(スクワレン)>
サメ肝油には、スクワレンやDHA、EPA(オメガ3系脂肪さん)が豊富に含まれています。
スクワレンには、抗酸化機能と酸素運搬機能があり、高コレステロール血症や心血管の疾患を抑える効果が認められています。
またDHA・EPAは、血液をサラサラにして、コレステロール値を下げて、善玉(HDL)コレステロールを増やす作用があるので、脂質異常症予防におすすめです。
<ヘルスライフ スーパーアトランティックフィッシュオイル>
スーパーアトランティックフィッシュオイルには、DHA・EPAがたっぷりと含有されています。
コレステロール値を下げて、善玉(HDL)コレステロールの数を増やしてくれるので、脂質異常症を予防、改善できるでしょう。
<ヘルスライフ ビルベリー(アントシアニン)>
ビルベリーエキスには脂肪合成や脂質の蓄積を抑制し、インスリンを介して脂肪細胞分化を抑制する働きが認められています。
つまりビルベリーには高コレステロール血症予防効果や肥満予防効果が期待できるというわけです。
脂質異常症予防にぴったりのサプリと言えるでしょう。
<ヘルスライフ コエンザイムQ10>
コエンザイムQ10は、脂溶性の抗酸化物質であり、ビタミンC、Eとともに強い抗酸化作用が期待できます。
活性酸素などのフリーラジカルから体を守り、悪玉(LDL)コレステロールの酸化を予防して、動脈硬化を防いでくれるでしょう。
<ヘルスライフ 月見草オイル>
月見草オイルには、必須脂肪酸であるγリノレン酸が豊富に含まれています。
このγリノレン酸から作られるプロスタグランジンE1には、血糖値やコレステロール値、血圧を下げる効果があり、生活習慣病予防や改善におすすめのサプリと言えるでしょう。
<ヘルスライフ ローヤルゼリー>
ローヤルゼリーは、高血圧や高コレステロール血症予防に有効です。
高コレステロール血症が引き起こされるメカニズムの1つが、肝臓でのリポタンパク質の過剰摂取があります。
酵素分解したローヤルゼリーはこのリポタンパク質の分泌を抑制する作用があるため、脂質異常症予防に効果があるのです。
<ヘルスライフ プロポリス>
プロポリスは肥満予防に効果を発揮してくれます。
プロポリスを摂取すると脂質代謝が改善され、体脂肪が蓄積しにくいように抑制してくれます。
つまり内臓脂肪を減らすことができ、中性脂肪を減らすことができるというわけ。
さらにプロポリスは、コレステロールを体内合成するHMG-CoA還元酵素というタンパク質の量も減少させるため、コレステロール量低下にも作用します。
食事からの脂質が吸収しにくくなることで、肥満・メタボを防ぎ、脂質異常症を予防できるでしょう。
<ヘルスライフ スピルリナ>
スピルリナは栄養バランスに優れた高タンパク質、ビタミン類、ミネラル類、酵素、アミノ酸などをたっぷりと含有しています。
また食物繊維や鉄分なども含まれており、脂質異常症予防におすすめの栄養素をバランスよく摂取できるでしょう。
またスピルリナには、血圧、血中脂質を減らす作用があります。
特にトリアシルグリセロールと悪玉(LDL)コレステロールを減少させる作用に優れており、間接的に総コレステロール、善玉(HDL)コレステロール値を改善する可能性が期待されています。
高血圧予防、高コレステロール血症、動脈硬化の予防にぴったりのサプリですね。
【まとめ】
脂質異常症は自覚症状がないため、健康診断などで発見されるケースがほとんどです。
症状が進行してしまうと、動脈硬化を発症するリスクも高くなってしまうので、早期に発見、治療をすることが望ましいでしょう。
定期的な健康診断は必ず受けるようにしたいですね。
また脂質異常症は生活習慣の改善によって、十分に予防できる病気でもあります。
規則正しい食生活で、適度な運動を心がけるようにしましょう。