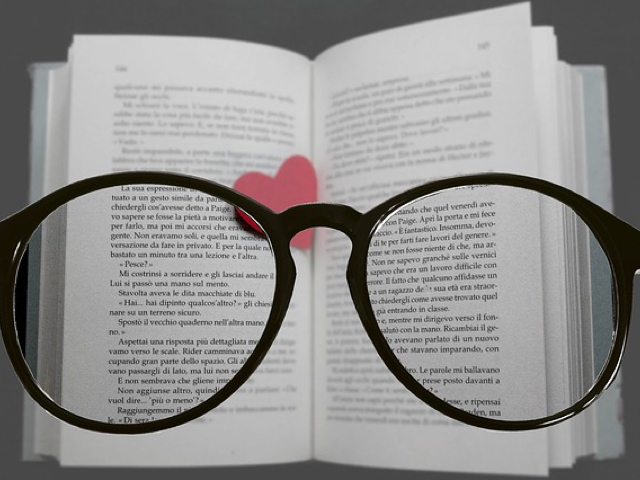風が吹くだけでも激痛が走る「痛風」とはどんな病気なの?痛風は生活習慣の改善で予防できる!!
2020年11月10日
目の2大疾病といえば白内障と緑内障!白内障と緑内障は名前は似ているけど全く別の病気!
2020年11月17日骨粗しょう症と言えば、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。
骨粗しょう症による骨折で、そのまま寝たきりになって介護が必要になるというケースもあるので、非常にやっかいな病気と言えるでしょう。
高齢の女性でよく起こる骨粗しょう症は、どのような原因で起こるのでしょうか?
また骨粗しょう症にならないようにするための効果的な予防対策はあるのでしょうか?
ここでは骨粗しょう症についての基礎知識と、予防方法、おすすめのサプリなどをまとめてみましょう。
目次
【骨粗しょう症ってどんな病気なの?】
骨粗しょう症は骨密度が低下して骨がスカスカの状態になり、骨折しやすくなる病気です。
骨は形成と吸収(破壊)のバランスで骨密度を保っていますが、骨の形成と吸収のバランスが崩れると、骨密度が急激に低下してしまうのです。
骨密度が低下した骨はスカスカの状態になり、ちょっとした衝撃でもすぐに骨折してしまいます。
骨粗しょう症になると、つまずいて手やひじをついたり、くしゃみをしたりと生活上ほんのちょっとの衝撃でも骨折してしまうのです。
現在我が国には約1,280万人もの骨粗しょう症患者さんがいると推定されています。
しかし実際に治療を受けている患者さんは約2割程度。
骨粗しょう症の正確な診断と適切な治療を受けることで、寝たきり生活や介護を受けたるリスクを減らすことができます。
特に女性の方は閉経後に骨粗しょう症を発症するリスクが高くなるので50歳を過ぎたあたりから定期的に骨量を測定する必要があるでしょう。
【なぜ骨粗しょう症は女性に多く発症するの?その理由は女性ホルモンにあり?!】
骨粗しょう症の日本における患者さんは約1,280万人です。
男女比を見てみると、男性380万人に対して、女性は900万人と圧倒的に女性がなりやすい病気と言えます。
この人数は人口の約10%に相当するので、骨粗しょう症はよくある病気であり、誰でも発症する可能性があるのです。
男女がかかる疾患のうちでも、最も性差のある疾患と言われていますよ。
日本人では50歳以上の女性の3人に1人は骨粗しょう症になると言われており、年代別では50代で9人に1人、60代で3人に1人、70代では2人に1人の割合で骨粗しょう症を発症します。
非常に高い確率で発症することが良く分かりますね。
ではなぜ女性骨粗しょう症を発症しやすいのでしょうか?
その理由は「女性ホルモン」が原因となっています。
私達の体の中では、血液などと同じように、骨でも絶えず新陳代謝が行われています。
骨の古くなった部分は、破骨細胞によって破壊(骨吸収)されて、骨芽細胞によって新しい骨入れ替わります。
これを骨形成と呼んでいます。
この骨吸収と、骨形成の一連の流れを「骨のリモデリング(再構築)」と呼んでいるのです。
骨吸収は約4週間、骨形成には約4ヶ月、骨のリモデリングには約5ヶ月かかります。
しかし骨吸収と骨形成のバランスが崩れてしまうと、骨の量が減少し、新しい骨の割合が少なくなるため、骨密度はスカスカの状態に。
骨の質は劣化して、骨から丈夫さやしなやかさが失われて骨粗しょう症を発症してしまうのです。
骨吸収と骨形成のバランスを崩す要因の1つが「女性ホルモン」。
女性ホルモンのエストロゲンには骨吸収(骨の破壊)を抑制する働きがあります。
女性では、50歳頃に閉経となり、
急激に女性ホルモンの分泌量が減少します。骨吸収を抑制する働きがあるエストロゲンの分泌量も減少してしまうため、骨吸収の歯止めが効かなくなり、骨の量がどんどん減少して、骨の質が劣化してしまうのです。
さらに加齢や背勝習慣の乱れ、生活習慣病の発症によっても骨は劣化しやすいので、骨密度はどんどんスカスカの状態になります。
骨粗しょう症は気づかないうちに徐々に進行していき、骨量、骨の質ともに低下して、ある日突然骨折を引き起こしてしまうのです。
【骨粗しょう症は骨密度の低下だけではなく、骨質も関係している】
骨粗しょう症=骨密度が低下して骨折しやすくなる病気という認識が強いですが、骨密度が正常範囲でも骨折リスクが高い患者さんもいることが明らかになってきています。
その原因を詳しく調べてみると、人によって骨質には違いがあり、骨質が低下している場合、骨折するリスクが高まることが分かったのです。
骨強度に関する割合は、骨密度:骨質=7:3とされています。
骨質が悪くなると骨のしなやかさは失われ、骨密度がいくら高くても骨折することがあるので注意しなければなりません。
つまり骨粗しょう症は骨密度の低下だけではなく、骨質の劣化も関与しており、その両方が影響して骨折リスクが高まるのです。
【骨粗しょう症になるとどんな症状が出るの?】
骨粗しょう症は自覚症状が現れにくく、静かに病気が進行していくため「サイレント・ディジーズ」とも呼ばれています。
骨が弱く、もろくなっていても痛みが出ない人も多いです。
骨粗しょう症の代表的な症状は以下の通りです。
・背中や腰が痛くなる
・背中や腰が丸くなる
・身長が縮む
・背中や腰の痛みで寝込むことが増える
・脆弱性骨折
初期では、背が縮んだ気がする、腰が曲がったような気がするという程度でも、病気が進行すると明らかに身長が縮む、背中や腰の曲がりを周囲から指摘されるようになるでしょう。
ただこの段階でも気づかない場合もあり、骨折して初めて骨粗しょう症と分かるケースが少なくありません。
症状に気づきにくいことが治療率の低さにつながっており、患者さんの約8割は骨粗しょう症の治療を受けていないとも言われています。
4㎝以上身長が縮んだという人は、骨密度検査やレントゲン検査を早めに受けるようにしましょう。
次に骨粗しょう症の症状として最も代表的な脆弱性骨折とそれに伴って起こる合併症についてまとめてみましょう。
<脆弱性骨折>
骨粗しょう症で最も問題となる症状は「脆弱性骨折」とそれに伴って起こる合併症です。
脆弱性骨折とは、わずかな衝撃など外力で生じる骨折のこと。
一般的には立った高さからの店頭を基準としていて、それより弱い力で骨折した場合「脆弱性骨折」と診断されます。
骨粗しょう症になると、転倒やくしゃみなどちょっとしたはずみで脆弱性骨折を起こしてしまうでしょう。
また脊椎の一部がスカスカになって、いつの間にか潰れてしまう圧迫骨折も多く起こります。
背が縮んだり、背中や腰に痛みが生じたりするのは、この脊椎の圧迫骨折が原因となっています。
<脆弱性骨折に伴って起こる合併症>
脆弱性骨折が起こると、全身で様々な影響を及ぼします。
背中や腰の曲がりや、背の縮みは内臓を圧迫して、呼吸器機能や消化機能の低下を引き起こしてしまいます。
消化機能の低下により胸やけや逆流性食道炎を起こすことがあるでしょう。
胃が圧迫されるため食欲減にもつながります。また呼吸器機能が低下することで、肺活量が減少し、身体全体の機能低下を引き起こすことも…。
足の付け根の骨折(大腿骨近位部骨折)の予後に関しては、骨折した患者の10%強が1年以内に死亡しているという結果報告されています。
太ももの付け根の骨折は骨折の中でも特に「寝たきり」になりやすく、骨粗しょう症になることで寝たきりになる確率は1.83倍も高まると言われているのです。
また骨粗しょう症で1度骨折を起こすと次々と骨折を起こす危険性が大きくなります。
太ももの付け根を骨折した女性が5年以内に再度骨折する危険性は、骨折をしたことのない女性に比べると16.9倍も高く、背骨を骨折した人は1年以内に5人に1人が再び骨折することが分かっています。
このように次々に骨折をすることを「骨折連鎖」と呼んでおり、1個の骨が折れていると周囲の骨にも負担がかかるようになり、2、3個とドミノ倒しのように骨折が連鎖してしまうのです。
骨粗しょう症によって起こる骨折はQOLや身体機能に大きく影響します。
骨折を繰り返すたびに健康状態はどんどん悪化してしまい、骨折を起こす前の状態に戻すことが難しくなってしまうでしょう。
骨粗しょう症は介護が必要となる人の原因の第3位にもなっており、骨折がきっかけで寝たきりになるリスクが非常に高いです。
寝たきりになってしまうと、今まで自分でできていたことができなくなり認知症やうつ病を患うリスクも高くなります。
【骨粗しょう症になるとどこの骨が折れやすくなるの?】
骨粗しょう症になるとどこの骨が折れやすくなるのでしょうか?
実は骨粗しょう症ではほぼ決まった部位が骨折します。
骨粗しょう症になって骨折が起こり始めるのは50歳代からですが、骨折しやすい部位は年代によって徐々に変化していきます。
年代別にまとめてみましょう。
<50歳代から>
・手首(橈骨)
・椎体(脊椎の骨の主要部)
椎体骨折は、自分の体重に背骨が耐え切れなくなり、気づかないうちに背骨がつぶれて起こる骨折です。
<65歳頃から>
・椎体
・前腕骨
・大腿骨近位部(太ももの付け根部分)
・上腕骨(肩からひじまでの骨)
大腿骨近位部(太ももの付け根部分)は、日常生活動作を最も悪化させる骨折であり、寝たきりになるリスクが高く、手術も必要です。
<75歳頃から>
・椎体
・大腿骨近位部
・前腕骨
・上腕骨
その中でも最も多いのが、椎体の骨折で約380万人もの患者さんが椎体の脆弱性骨折を起こします。
次に多いのが大腿骨骨折で、約17.6万人が罹患します。
【骨粗しょう症の検査・診断とは?】
骨粗しょう症はいくつかの検査が行われます。
早速まとめてみましょう。
<骨密度検査>
骨粗しょう症が疑われる場合、骨密度検査を行います。
骨密度は骨の強さを判定する代表的な指標であり、骨密度検査では骨の中にカルシウムやミネラルがどれくらい含まれているかを測定することができるのです。
骨密度は、若い人(20歳~40歳)の骨密度の平均値と比べて何%であるかで表されます。
骨密度が80%以上であれば正常。
ここでは代表的な骨密度検査方法をまとめてみましょう。
・DXA(デキサ)法
エネルギーの低い2種類のX線を当てて、骨を通過できなかったX線量から骨密度を測定する方法です。
全身のほとんどの骨密度が測定可能で、腰椎や大腿骨近位部の骨密度を正確に測ることができると言われています。
信頼度の高い骨密度検査と言えるでしょう。
・超音波法
かかとやすねの骨に超音波をあてて計測。
骨粗しょう症の検診で用いられることが多く、X線を使用しないため妊娠中でも測定可能。
・MD(エムディ)法
X線を使って手の骨と厚さの異なるアルミニウム板を同時に撮影し、骨とアルミニウムの濃度を比較して測定。
クリニックなどで簡単に計測できるため普及しています。
・定量的CT測定法(QCT法)
X線CT装置を使った測定法。
海綿骨と皮質骨という骨の構造に分けて骨密度を測定することができます。
<レントゲン検査>
背骨(胸椎、腰椎)のX線写真を撮って、骨折、骨のつぶれ、変形の有無、骨粗しょう化(骨にスが入ったようにスカスカになる状態)の有無を確認します。
レントゲン検査は他の病気と区別するために必要不可欠です。
<身長測定>
25歳時の身長と比べてどれくらい縮んでいるかを測定します。
<骨代謝マーカー検査>
血液検査や尿検査で、骨が作られたり、溶けだしたりする骨代謝(骨の新陳代謝)のバランスを検査します。
骨吸収を示す骨代謝のマーカーが高いということは、骨密度の低下速度が速いということ。
現在の骨密度の値にかかわらず骨折するリスクが高くなっていることを示しています。
骨代謝マーカーの検査は、骨粗しょう症を他の病気と区別するためにも必要な検査です。
骨粗しょう症が疑われる場合、このような検査を行い、骨密度と骨折の有無によって診断されます。
骨折は本人が自覚していない脆弱性骨折の場合もあるため、レントゲン検査で確認します。
【骨粗しょう症になりやすい人ってどんな人?その要因とは?】
骨粗しょう症は閉経後の女性がなりやすいということは分かりましたね。
実は骨粗しょう症は女性ホルモンの影響の他にも、生活習慣など環境要因などで発症リスクが高まるのです。
ここでは骨粗しょう症になりやすい要因についてまとめてみましょう。
<遺伝・骨折経験>
骨粗しょう症は遺伝の影響を受けます。
特に母親や母方の祖母などに骨粗しょう症による骨折(特に代々骨近位部骨折)や罹患があるケースでは、骨粗しょう症にかかる可能性は高いです。
<体型・骨密度>
体型が小柄な人は、骨が小さいためカルシウムの蓄積量が少ない傾向にあります。
さらにやせ型で筋肉の少ない人は、骨を支える力が弱いため、骨が弱くなりやすいです。
骨量は小学校高学年から20歳前後までの成長期に一気に増えるため、この時期に極端なダイエットをしてしまうと、カルシウムやビタミンDなど骨を形成するための栄養素が不足してしまいます。
また骨を作る細胞を活性化させる女性ホルモン分泌も減少するなど、思春期の極端なダイエットは骨の形成に大きな悪影響を及ぼしてしまうでしょう。
この時期に無理なダイエットをしてしまうと、骨粗しょう症になるリスクを高めてしまいます。
<女性>
男性に比べて女性は骨が細く、筋肉量も少ないことから、相対的に骨粗しょう症にかかるリスクが高いです。
ただ男性だからと言って骨粗しょう症にかからないというわけではありません。
糖尿病などの生活習慣病の影響によって骨質が悪くなると、骨密度に余裕があっても骨粗しょう症につながるでしょう。
男性では80歳を過ぎると骨粗しょう症患者が急増すると言われているので注意が必要です。
<閉経>
女性ホルモンの1つであるエストロゲンは骨にカルシウムを蓄える骨形成を促し、骨からカルシウムが溶け出す骨吸収を抑制する働きがあります。
閉経が起こるとこのエストロゲン分泌量は急激に減少。
そのため骨吸収が進み、骨粗しょう症になるリスクが高まるのです。
また、閉経以外にも無月経や生理不順の女性もエストロゲン分泌量は少なくなるため、骨粗しょう症を発症する危険性は高くなるでしょう。
<加齢>
男性でも女性でも、成長期に骨は活発な代謝を繰り返し増加します。
20歳前後で最大骨量に達し、その後40代半ばくらいまでは一定の骨量を維持します。
その後は加齢とともに徐々に骨量は減少するため、加齢に伴って骨粗しょう症にかかりやすくなるでしょう。
加齢による骨量の減少はスピードを遅らせることはできても、完全に食い止めることはできません。
<喫煙>
喫煙は胃腸でのカルシウムの吸収を阻害してしまいます。
また女性ホルモンのエストロゲン分泌も抑制してしまうため、骨量不足を引き起こしてしまうでしょう。
<過度な飲酒>
アルコールを過剰に摂取してしまうと、胃腸でカルシウムが吸収されにくくなります。
またアルコールの利尿作用によって、尿と一緒にカルシウムが体外へ排泄されてしまうので骨量低下につながりやすいです。
日本酒であれば1合、ビールなら中ビン1本、ワインならグラス2杯、焼酎なら0.6合程度の適度な飲酒にとどめておきましょう。
<運動不足>
運動不足の人は、骨を鍛えるための負荷をかける機会が少ないため、骨の強度が低くなります。
また筋力やバランス力も低下してしまうため、転倒や骨折の危険性が高まるでしょう。
<偏った食生活>
インスタント食品やジャンクフードなど食塩やリンを多く含む食べ物をたくさん摂取すると、骨に必要なカルシウムが不足します。
またカルシウムの吸収率も下がると言われています。
【骨粗しょう症の治療方法とは?】
骨粗しょう症の治療の目的は、骨密度の低下を抑えて、骨折を防ぐことです。
骨粗しょう症の治療方法は
・食事療法
・運動療法
・薬物療法
を組み合わせて行うのが一般的で、どれも重要な治療になります。
それぞれの治療方法についてまとめてみましょう。
<食事療法>
骨粗しょう症の食事療法では、カルシウムをはじめとして様々な栄養素をバランスよく摂取することが大切です。
ここでは骨粗しょう症の食事療法で積極的に摂取したい栄養成分をご紹介しましょう。
・カルシウム
骨粗しょう症の食事療法ではカルシウムの摂取が欠かせません。
カルシウムは骨を造っている栄養素であり、骨粗しょう症予防や治療には必須成分です。
成人男性では1日650~800㎎、成人女性では1日650㎎を摂取することが推奨されています。
丈夫な骨を保つためにはこの推奨用量よりも100g上乗せして、1日700~800㎎のカルシウムを摂取するのが望ましいでしょう。
ただし摂取のしすぎには注意が必要です。
カルシウムを多く含む食品:牛乳・乳製品、小魚、干しエビ、緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜)、大豆・大豆製品
・ビタミンD
カルシウムの吸収を助ける働きをするビタミンDも積極的に摂取したい栄養素の1つ。
カルシウムとビタミンDを同時に摂取することで、腸管でのカルシウム吸収率がアップします。
ビタミンDを多く含む食品:魚類(サケ、うなぎ、サンマ、メカジキ、イサキ、カレイ)、キノコ類(椎茸、キクラゲ)、卵
・ビタミンK
ビタミンKは、骨を造るのに重要な働きをします。
ビタミンKを多く含む食品:納豆、緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜、ニラ、ブロッコリー)サニーレタス、キャベツ
・タンパク質
タンパク質の摂取量が少なくなると、骨密度低下を助長してしまいます。
意識的に良質なタンパク質の摂取を心がけましょう。
タンパク質を多く含む食品:肉、魚、卵、豆類、牛乳・乳製品
これ以外にもビタミンやミネラルなどをバランスよく含んだ食事を規則的に1日3食摂取するのが大切です。
<運動療法>
運動することで、筋力が増強し、バランス感覚がアップします。
そうすることで転倒しにくくなり、骨折のリスクを回避できるのです。
また骨は負荷がかかるほど、強くなる性質があります。
さらに運動を続けると血流がよくなるため、骨を作る細胞が活発になり、骨が生成されやすくなるでしょう。
散歩をしたり、階段の上り下りをしたりと日常生活の中で運動量を増やすのがおすすめ。
適度に日光に当たると、カルシウムの吸収をよくするビタミンDが活性化されるので強い骨作りに役立ちますよ。
ただ運動する時には無理は禁物。体の状態に合わせて無理なく続けることが大切です。
ここでは骨粗しょう症患者さんにおすすめの運動方法をご紹介しましょう。
・開眼片脚立ち運動(ダイナミック・フラミンゴ体操)
1、フラミンゴのように片脚で立つ(床につかない程度に片脚をあげる)
2、目を開けたまま、片方の脚で左右各1分間立つ
3、1日3セット行う
片脚立ちをする際には、転倒しないように、壁やテーブルなどにつかまりながら行います。
また姿勢をまっすぐにして行うようにしましょう。
体重を片脚に乗せることで、両足立ちする時に比べて倍の負荷をかけることができ、骨が強くなるでしょう。
またバランス感覚もアップするので、転倒予防にもつながりますよ。
このダイナミック・フラミンゴ体操は、運動器の障害による要介護の状態や介護リスクが高い状態の対処法として注目されています。
・ふくらはぎ、アキレス腱のストレッチ
1、壁に手を付く
2、前に出した方の脚の膝を曲げて、体重をかけていき、後ろの方の脚のふくらはぎを伸ばす
3、後ろの方の脚の膝を曲げて、アキレス腱を伸ばす
4、片脚30~40秒ずつ伸ばし、左右交互に行う
・背筋を伸ばすストレッチ
背筋を伸ばすストレッチは立った姿勢もしくは椅子に座って行います。
1、立った姿勢で壁から20~30㎝離れて、壁に沿って両手をできるだけ上に挙げて、背筋を伸ばす
2、椅子に座って、頭の後ろで手を組み、両膝をできるだけ後ろに引いて胸をゆっくりと開く
<薬物療法>
骨粗しょう症の薬は、骨吸収を抑制する薬と骨の形成を促進する薬があります。
代表的な薬剤をご紹介しましょう。
・カルシウム製剤
カルシウムは骨を作る主要成分です。
食事の摂取と薬の摂取を合わせて1,000㎎が望ましいと言われています。
・ビタミンK2製剤
骨形成を促進する作用があり、骨折の予防効果があります。
ただ骨密度を著しく増加させるわけではありません。
・活性型ビタミンD3製剤
食事で摂取したカルシムは腸内に吸収されにくいです。
そこで活性型ビタミンD3製剤を服用することで、腸管からのカルシウム吸収を増加させます。
また骨形成と骨吸収のgバランスを調整する作用もあり、骨粗しょう症治療薬としては古くから用いられています。
・女性ホルモン製剤(エストロゲン)
女性ホルモンの減少に伴って起こった骨粗しょう症に有効な治療薬。
閉経後の更年期症状を緩和し、骨吸収を抑制するエストロゲンを補給することで骨密度の低下を防ぎます。
・ビスフォスフォネート製剤
破骨細胞に作用して、過剰な骨吸収を抑制することで骨密度を増やします。
経口剤、注射剤などがあり、服用方法も1日1回、1週間に1回、4週間に1回など様々です。
・SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)
塩酸ラロキシフェン、バゼドキシフェン酢酸塩のことで、エストロゲンと似た作用で、骨吸収を抑制することで骨密度を増加させます。
乳房や子宮など骨以外の臓器への影響はなし。
・カルシトニン製剤
骨のカルシウムが体内に溶けだすのを抑制する注射薬。
強い鎮痛作用があり、骨粗しょう症に伴う背中や腰の痛みを緩和してくれます。
・デノスマブ(抗ランクル抗体薬)
破骨細胞の形成や活性化に関与しているLANKリガンドというタンパク質に作用。
骨吸収を抑制することが可能。6ヶ月に1回の皮下注射なので、継続しやすいです。
・テリパラチド(副甲状腺ホルモン)
新しい骨を作る骨芽細胞を活性化させて、骨強度を高めることができます。
骨密度が非常に低く、骨折リスクが高い患者さんに適した薬。
骨粗しょう症の薬物治療は、根気よく続けることが大切。
1年・2年~といった息の長い治療で効果が現れるため、即効性を感じにくいです。
そのため途中で服薬をやめてしまう患者さんが非常に多く、治療1年後には約5割が処方通りの服薬ができていないと言われていて、5年後には約半数が服薬を辞めてしまうそう。
骨密度がなかなか上がらないからと言って勝手に自己判断で薬を中断してはいけません。
効果的に治療をするために、医師の指示通りに根気強く服薬するようにしましょう。
【骨粗しょう症を予防するには?簡単にできる予防方法とは?】
骨粗しょう症を予防するためにはどのようなことに気を付ければよいでしょうか?
自分でできる予防方法をまとめてみましょう。
<若い頃に無理なダイエットをせず骨の貯金をする>
10代は食事でカルシウムを摂取し骨の貯金をする時期です。
骨密度が最も増加する思春期の生活習慣は非常に重要で、カルシウムを積極的に摂取しましょう。
また骨量を増やすために荷重のかかる運動も積極的に行います。
思春期に食事制限など無理なダイエットをすると、骨の形成の大きな妨げとなるため、食事量を減らさずに運動量を増やしたダイエットをしましょう。
<禁煙&禁酒>
喫煙はカルシウム吸収を抑制してしまうので、喫煙習慣のある人はすぐに禁煙しましょう。
お酒は利尿作用があるため、飲みすぎると骨形成に必要なカルシウムまで排泄されてしまいます。
さらに腸からのカルシウム吸収も妨げてしまうので過度なアルコール摂取は控えた方がよいでしょう。
<適度な運動を習慣化する>
日光を浴びながらのウォーキングなど、適度な運動を毎日継続しましょう。
骨に適度な圧力を加えることで骨が強くなります。
また日光を浴びることでビタミンDが活性化されるためカルシウム吸収率がアップするでしょう。
運動をすれば筋肉もつき、身のこなしがスムーズになるため、転倒しにくくなり、骨折防止にもつながりますよ。
<定期的な検査を受ける>
40代になると骨量は徐々に減少していくため、定期的な検査を受診しましょう。
自分の骨の状態を定期的にチェックしておくことで、早期発見・早期治療につながります。
日本では40歳以降の女性を対象に5年刻みに骨密度の検診を行っている自治体が多いです。
特に閉経後の女性は、1年に1度は検診を受けると安心ですね。
<骨折しにくい住環境を整備する>
骨粗しょう症において一番怖いのは転倒による骨折です。
高齢者の多くは、家の中で転倒・骨折しているので、住環境を見直して骨折しにくいように工夫しておきましょう。
例えば自宅においては
・手すりをつける
・段差をなくす
・照明を増やす
といった対策がおすすめです。
またこけやすいサンダルやスリッパはやめて、楽に脱ぎ履きできるものを選びます。
服装も裾の絡まりやすい服は避け、手ぶらになれるようにリュックなどを活用するとよいでしょう。
<塩分の多い食事、インスタント食品、カフェインは控える>
塩分の多い食品やインスタント食品、スナック菓子などにはリンが含まれており、カルシウム吸収を阻害してしまうため、控えるようにしましょう。
またコーヒーや紅茶などカフェインを多く含む食品も摂りすぎには注意が必要です。
<骨質を支えるコラーゲンの劣化防ぐ栄養素の摂取>
骨を丈夫にするためには、骨のコラーゲンの劣化を防ぐことが大切。
骨のコラーゲンの劣化を防ぐと骨質を維持することができます。
骨のコラーゲン劣化予防におすすめの栄養素は
・ビタミンB6
・ビタミンB12
・葉酸
などです。
これらの栄養素を十分に摂取すれば骨を丈夫にすることができ、動脈硬化や心臓病リスク低下にもつながります。
【骨粗しょう症予防におすすめのサプリメントはある?】
当店で取り扱うサプリメントの中で、骨粗しょう症予防におすすめの商品をご紹介しましょう。
<ヘルスライフ スーパーアトランティックフィッシュオイル>
ヘルスライフ社のスーパーアトランティックフィッシュオイルは、ニュージーランド産の天然フィッシュオイルを含有したサプリメント。
魚に豊富に含まれるDHA、EPA、DPAをなどのオメガ脂肪酸をたっぷり配合しています。
フィッシュオイルに多く含まれる「多価不飽和脂肪酸(PUFA)」には、骨折を予防する効果があることが分かっており、骨粗しょう症予防にも効果が期待できます。
<ヘルスライフ マリンコラーゲン>
ヘルスライフ社のマリンコラーゲンは、100%ピュア天然コラーゲンを厳選配合。
1粒あたり130㎎のコラーゲン成分を配合しています。
コラーゲンは全タンパク質の約30%を占めており、そのうちの40%は皮膚、20%は骨や軟骨に存在しています。
骨を丈夫にするためには、骨のコラーゲンの劣化を防ぐことが大切。
骨のコラーゲンの劣化を防げば骨質を維持することができます。
フィッシュコラーゲンを摂取することで骨粗しょう症予防と改善に効果が期待できるでしょう。
<ヘルスライフ ビルベリー>
ヘルスライフ社のビルベリーは1粒770㎎のカプセルにビルベリーを5,000㎎配合。
このビルベリーはブルーベリーよりの約2~5倍のアントシアニンを含有していることで有名です。
アントシアニンを継続的に摂取すれば骨の減少を抑えられる可能性があることが報告されており、骨粗しょう症の予防効果が期待できます。
<ヘルスライフ ローヤルゼリー>
ヘルスライフ社のローヤルゼリーは、最高級のロイヤルゼリーを配合しており、デセン酸の平均含有量は6%相当となっています。
ローヤルゼリーを摂取すると、骨密度の減少が抑えられ、投与量に比例して骨中のカルシウム量が増加すると研究結果が報告されております。
これはローヤルゼリーに含まれる脂肪酸「10-ヒドロキシ-2-デセン酸」に骨破壊を抑制する働きがあるためです。
ローヤルゼリーは骨粗しょう症予防に有効であると言えるでしょう。
<プロバイオティクス>
ライフスペースのブロード スペクトラム プロバイオティクスは1カプセルに320億個の善玉菌を配合しているオーストラリアで人気No1のプロバイオティクスのサプリです。
プロバイオティクスは高齢女性の骨格を保護し、骨損失を抑制すると報告されており、骨粗しょう症の進行予防に効果的で安全なサプリといえるでしょう。
<ヘルスライフ コエンザイムQ10>
ヘルスライフ社のコエンザイムQ10は1,200㎎のカプセル1粒にコエンザイムQ10を320g配合。
コエンザイムQ10とカルシウムやコラーゲンを主成分としたサプリを6ヶ月摂取すると骨密度が改善したという報告があります。
コエンザイムQ10とコラーゲンを同時摂取することで、カルシウムが吸着されやすい状態になって、骨密度が改善するため、骨粗しょう症予防に役立つでしょう。
さらにこちらのサプリにはビタミンDも配合されています。
ビタミンDは腸内でのカルシウム吸収を促進するので、カルシウム吸収率がアップ。
骨粗しょう症には欠かせないビタミンの1つですので、一緒に摂取できるのは嬉しいですね。
<ブラックモアズ バイオC1,000mg>
ブラックモアズ社のバイオC1,000mgはビタミンCを手軽に摂取できるビタミンCサプリメントです。
さらにバイオC1,000mgにはビタミンCだけではなく、カルシウムなどのミネラル群もバランスよく配合。
シトラスやアセロラ、ローズヒップ成分なども配合していて、骨粗しょう症予防に最適です。
【まとめ】
骨粗しょう症は閉経後の女性によく起こる病気であり、早期発見・早期治療によって骨折などのリスクを減らすことができます。
また生活習慣の改善で予防できるので、食生活や運動などできることから始めてみましょう。