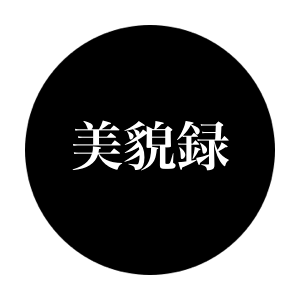
フェルラ酸の効果と効能、作用について
2018年3月30日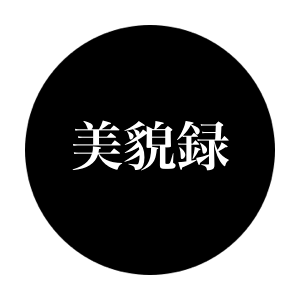
プラセンタの効果と効能、作用について その1
2018年3月30日ブドウ(葡萄)はブドウ科の低木になる果実のことで、秋のフルーツとして知られています。
ブドウの主な働きは、ポリフェノール成分が多く含まれており、生活習慣病を改善したりする役割があります。
そのほかミネラル類や有機酸を豊富に含んでいるため、健康を増進するには利用できる食品として知られています。
そのため、こうした効果効能を手に入れるために、適切な量のブドウの摂取を食生活に取り入れていくことが大切です。
ブドウは紀元前1億4000年ごろには出現されていたとされる、世界最古の果物の一つに数えられています。
日本では鎌倉時代にはで栽培されており現在でも名産地となっています。
こうしたブドウはそのまま食べることができるほか、レーズンとして加工したり、
ジュースやワインとして飲まれるようになっています。
そして、ブドウにはアントシアニンやレスベラトロールなどの
ポリフェノールが豊富に含まれていることから健康にも良いと注目されています。
ブドウは生活習慣病を改善する役割のほか、以下のような効果効能があります。
ブドウ(葡萄)の主な効果/効能/作用
・目の健康を増進する(アントシアニンが豊富に含まれているため)
・疲労回復につながる(ブドウ糖がエネルギー源となるため)
・下痢を予防する(タンニンが悪玉菌を減少させるため)
・排尿を促す(肝機能や腎機能を高めるため)
・老化を防ぐ(抗酸化作用があるため)
このようにブドウには、たくさんの効果効能があるため健康を維持時増進するためにも注目されています。
ただし、ブドウの過剰摂取は腹痛や下痢などを引き起こす可能性もあるので注意が必要です。
そのため、摂取量の目安としては1日に100g程度がいいとされています。
これは大粒のブドウで7~8粒、小ぶりのブドウで10粒程度となっています。
ただし、こうしたブドウを食すことが難しい場合などは、グレープシードオイルなどを調理に使うこともいいでしょう。
また、ブドウ成分を凝縮した「サプリメント」も販売されているので摂取すると、
効率的に栄養価を得ることができるので試してみるのもお勧めです。
