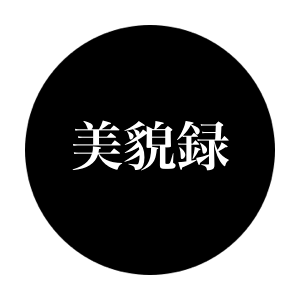
リボフラビン(ビタミンB2)の効果と効能、作用について
2019年1月12日
ローズヒップオイルは敏感肌でも使える♪お手入れ最後の保湿ケアにおすすめ!
2019年1月14日納豆は発酵食品の一種です。
日本が発祥となっており、諸説あるものの、弥生時代から食されていたともいう古い歴史をもつ食べ物です。
その昔、納所で作られた豆は、桶や壺などに貯蔵され、お寺に納められていたといいます。
「納めた豆」が納豆の由来と考えられています。
発祥の地に関しても諸説あり、秋田県もしくは茨城県、熊本県と3つの地域との関連性が深いです。
納豆は作り方によって大きく2種類に分けることができます。
一つめは、納豆菌で発酵させている「糸引き納豆」です。
粘り気があり糸を引くことからそう呼ばれています。
二つめは、大豆と小麦、麹菌を塩水に漬けることで発酵させる「寺納豆」です。
塩辛納豆、塩納豆、干し納豆などが挙げられます。
糸引き納豆のような粘り気はないものの、特有の塩味が特徴的です。
混同されがちな「甘納豆」は、大豆を砂糖で煮詰めることで作られたものです。
糸引き納豆や寺納豆のように発酵させたものではないため、全く別の食品と考えられています。
家庭でもっともなじみ深い糸引き納豆は、実際の製品では製造過程や大きさ、豆の種類、容器などでさらに細分化されています。
目次
糸引き納豆の種類
製造過程
・丸大豆納豆(大豆をそのまま煮て発酵させたもの)
・ひきわり納豆(大豆を細かく砕き、表皮を剥く過程を経たもの)
・五斗納豆(ひきわり納豆に麹や塩を入れて発酵させたもの。山形県米沢地区の郷土食)
大きさ
・超極小粒
・極小粒
・小粒
・中粒
・大粒
(サイズは製造元によって差があります)
豆の種類
・黄大豆
・青大豆
・黒豆
・赤大豆
・茶大豆
容器
・発砲スチロール
・藁
・経木(木材を紙のように薄く削ってできたもの)
近年、健康志向の高まりに伴い、納豆ブームが再来しているといいます。
それにつれて製品の多様化も進み、チーズやわさび、カレーなどの味付けを加えたユニークな納豆も人気を集めています。
納豆の主な効果/効能/作用
納豆は古来より重要なタンパク源であったとされています。
特に、主材料である大豆の栄養素の高さがさまざまな効果をもたらします。
納豆にはタンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維といった5大栄養素が含まれています。
それだけでなく、糸引き納豆の発酵に用いられる納豆菌はさまざまな酵素を生み出します。
これら酵素にも健康維持に役立つ作用があると考えられています。
・疲労回復
納豆に含まれるビタミンB群は「疲労回復ビタミン」とも呼ばれており、皮膚や粘膜などの健康維持に関わっています。
不足することで疲れやすくなる、集中力の低下などの症状がみられます。
特に、糖質をエネルギーに変えるビタミンB1、糖質や脂質の代謝を促進するビタミンB2、タンパク質をエネルギーに変えるビタミンB6が疲労回復に効果的です。
また、ビオチンには筋肉痛を緩和する効果があるとされています。
ビタミンB群の働きには相互関係が影響するため、複合的に摂ることが望ましいです。
・腸内環境を整える
納豆2〜3粒の中におよそ100億個もの納豆菌が生息しているといいます。
納豆菌は腸内で善玉菌として働くため、高い整腸作用があります。
熱や胃酸に強い性質をもっており、死滅した状態で腸に届くことはあまりありません。
腸内を酸性に変えていくため、腸内の悪玉菌が減り善玉菌が増殖しやすくなるのです。
乳酸菌やビフィズス菌なども活性化し、腸内環境の改善に役立ちます。
さらに、抗菌作用もあるため、サルモネラ菌やチフス菌、赤痢菌、病原性大腸菌O-157などの抗菌作用も期待できます。
腸内フローラが良好になることで、大腸がんの予防にも繋がります。
・脳卒中、高血圧の予防
発酵させることで発生する酵素、「ナットウキナーゼ」には血管中の血栓を溶かす効果があります。
人工的な血栓であれば、瞬時に溶解するほどの強い力を持っており、これはすべての大豆食品の中でも納豆だけだと考えられています。
従って、納豆には脳卒中(脳梗塞や脳出血)を予防する効果も期待されています。
また、血流が改善されることで、血圧低下にも繋がります。
高血圧の原因としてナトリウムの過剰摂取が挙げられます。
納豆に含まれるカリウムにはナトリウムを体外に排出させる作用があるため、血圧を下げる効果が期待できます。
・骨の形成を促進する
納豆に多く含まれるビタミンの一つが「ビタミンK」です。
カルシウムとタンパク質の結合を高め、カルシウムを骨に吸着させることで骨の形成を促進させます。
ビタミンKにはビタミンK1とビタミンK2の2種類があり、このうち骨の形成に大きく関わるのは発酵食品に含まれるビタミンK2の方です。
また、血液凝固作用もあり、不足することで怪我をしたときなどに血が止まりにくくなってしまいます。
・心臓病、動脈硬化の予防
動脈硬化は血中に悪玉コレステロール(LDL)が蓄積することによって起こります。
「レシチン」には肝機能を高める作用があり、血中のコレステロールが血管壁に滞留するのを防ぎます。
悪玉コレステロールを除去し、善玉コレステロール(HDL)を増加させる働きをしてくれます。
このことから、動脈硬化の予防に効果的だと考えられているのです。
ビタミンKにはタンパク質の一種「マトリックスGlaタンパク」を活性化する作用もあります。
このタンパク質にも動脈硬化や心臓病を予防する効果があるとされています。
ほかにも、大豆に多く含まれるポリフェノールの一種「イソフラボン」は乳がんや前立腺がんを予防するのに効果的です。
抗菌ペプチドという納豆由来の物質がガン細胞を殺傷するという研究結果も出ています。
・糖尿病、肥満の予防
ビタミンB1は脂肪燃焼にかかわる補酵素で、不足することで糖質が中性脂肪として肝臓に合成されていきます。
体脂肪を減らし肥満の原因を排除するために欠かせない栄養素です。
ビタミンB2には血糖値の上昇を抑制するのに効果的です。
また、レシチンはインスリンの分泌を促進する作用があるため、糖質の吸収を妨げてくれます。
血糖値が急激に上昇、低下することで発生する病気として糖尿病が知られています。
これらの栄養素が含まれる納豆には、その予防効果が期待できるでしょう。
・認知症の予防
糖尿病の人は認知症になりやすく、またその逆の傾向にあるとされています。
すなわち、血糖値が正常化することで認知症リスクも低減させられるということです。
納豆の血糖値を安定させる効果が、認知症予防にも役立つでしょう。
さらに、レシチンに含まれる「コリン」は脳の伝達物質である「アセチルコリン」の材料となります。
アセチルコリンの減少はアルツハイマー型認知症の原因の一つといわれています。
よって、レシチンは脳の働きを活性化し、記憶力や集中力、学習能力などを維持するために必要不可欠といえます。
・美肌、肌荒れの予防
イソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをし、若々しい肌を保つのに効果を発揮します。
シワやたるみ、肌荒れなどを防ぐのに役立ちます。
更年期に入った女性はエストロゲンの分泌が急激に衰えるため、骨粗しょう症のリスクが高まります。
イソフラボンを摂取することで肌老化だけでなく、重大な病気を予防していくことが可能です。
・アンチエイジング、長寿
納豆の成分で注目されているのが「ポリアミン」です。
ポリアミンには動脈硬化の促進を抑制するだけでなく、老化を防止するアンチエイジング効果もあるとされています。
マウスの実験により、ポリアミンを摂取した個体の方が、外見が若返り、生存率も高くなったと判明しています。







