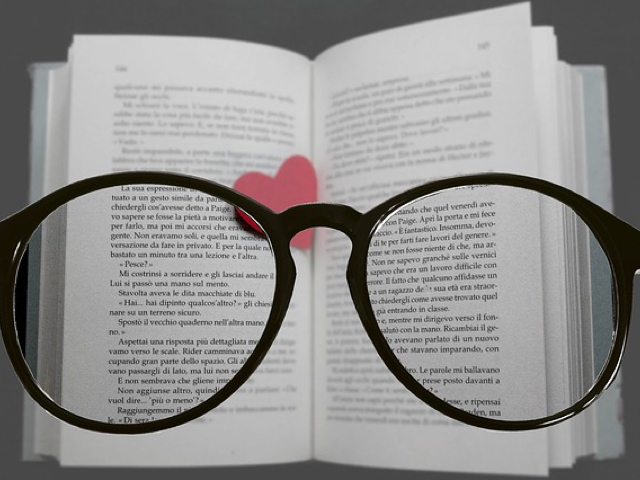女性との会話も弾む!アールグレイ スペシャルティー 追記レビュー
2018年11月13日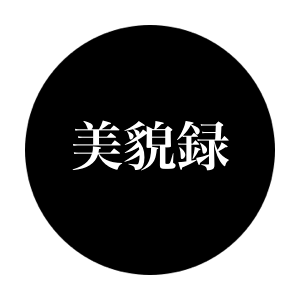
ビオチン(ビタミンB7)の効果と効能、作用について
2018年11月14日DHAとEPAは、主に青魚に多く含まれる脂肪酸の一種です。
DHAは「ドコサヘキサエン酸」の略称で、近年ではドロドロ血液を改善するサラサラ成分としても有名で、青魚だけでなく人間の母乳にも多く含まれています。
また体内ではEPAから変換されることでDHAが生成されますが、変換率が低いため生成量も少ないという特徴があります。
EPAは「エイコサペンタエン酸」の略称で、DHAと同じくサラサラ成分として有名です。
目次
◆DHAとEPAは必須脂肪酸の一種
DHAとEPAは体内でほとんど生成できない脂肪酸であるため、食品などから摂取する必要がある必須脂肪酸でもあります。
そもそも脂肪酸とは脂質を作り出す素となる成分で、「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2種類に大きく分類され、不飽和脂肪酸は「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」の2種類に分類され、さらに多価不飽和脂肪酸は「n-3系(ω-3系)脂肪酸」と「n-6系(ω-6系)脂肪酸」の2種類に分類されています。
■飽和脂肪酸…主に肉や油などの動物性脂肪に含まれ、常温では固体で存在。過剰摂取で肥満や糖尿病、動脈硬化を招く。
■不飽和脂肪酸
□一価不飽和脂肪酸…オリーブ油やひまわり油に含まれ、血液中のコレステロール値を下げる作用に優れている。
□多価不飽和脂肪酸
◎n-3系(ω-3系)脂肪酸…青魚や大豆に含まれ、血液をサラサラの状態に保ち動脈硬化や高血圧、高脂血症を予防する。
◎n-6系(ω-6系)脂肪酸…大豆油やコーン油などに含まれ、コレステロール値を下げる作用に優れている。
このように細かく分類されている脂肪酸のうちDHAとEPAは多価不飽和脂肪酸の一種であるn-3系(ω-6系)脂肪酸に属します。
◆DHAの主な作用/効果/効能
DHAは体内では主に脳や心筋、目の網膜、胎盤、精子、母乳などに含まれ、特に脳の神経組織に最も多く含まれています。
そのためDHAは脳機能を維持するうえで欠かせない重要な成分であるほか、次のような様々な作用や効果・効能を発揮します。
◎脳機能を活性化させる
DHAは脳の神経組織に多く含まれ、神経伝達物質であるシナプスの素となり脳細胞を活性化させる働きがあります。
そのためDHAを積極的に摂取することで脳機能が活性化され、学習機能や認知機能が向上するほか、抗うつ作用も発揮します。
◎血液サラサラ作用
血液中の中性脂肪値やコレステロール値が高いとドロドロ血液となり、高血圧や糖尿病、動脈硬化を招く原因にもなります。
DHAにはドロドロ血液の原因となる中性脂肪値やコレステロール値を下げる作用や血管壁や細胞膜を柔らかくする作用があり、健康的なサラサラ血液へと導く効果を発揮します。
◎血管疾患&がん予防
DHAが持つ血液サラサラ作用により動脈硬化が予防されることで、動脈硬化によって引き起こされる心筋梗塞や脳梗塞といった心血管疾患や脳血管疾患も予防することができます。
さらにDHAには身体の細胞の錆びを防ぐ抗酸化作用も優れており、細胞のがん化や増殖を防ぐ効果もあります。
◎抗炎症&抗アレルギー作用
DHAには炎症を抑制する作用があり、特に花粉症の症状である鼻水の原因となる「ロイコトリエン」というアレルギー関連物質の働きを抑制して花粉症を予防・改善させる効果があります。
◎目の健康を維持
DHAは目の網膜や視神経にも多く含まれているため、積極的に摂取することで網膜や視神経の機能を向上させて目の健康を維持することができます。
◎胎児の発育促進
DHAには脳機能を活性化させる働きがあることから、妊娠中の女性が積極的に摂取すると胎児の脳の発育を促進させることができます。
さらに早産や低体重のリスクを下げる効果もあります。
DHAにはこういった作用や効果・効能があることから、次のような方々に積極的な摂取が推奨されています。
・生活習慣病を予防したい方
・加齢と共に衰える脳機能を維持したい方
・妊娠中の女性
・脳や身体が成長中のお子様
続いて後半ではEPAの主な作用や効果、DHAとEPAの摂取目安量やおすすめ食材をご紹介します。
DHAとEPAを効率よく取るなら!GMP認可のこちらのサプリメントがおすすめ!
前半ではDHAとEPAが属する脂肪酸の種類、DHAの主な作用や効果についてご紹介しました。
後半では引き続きEPAの主な作用や効果、DHAとEPAの摂取目安量やおススメ食材についてご紹介します。
◆EPAの主な作用/効果/効能
◎血液サラサラ作用
EPAにはDHAと同じくドロドロ血液をサラサラにする作用があります。
ドロドロ血液は血管自体にも負担をかけ、血管を老化させて動脈硬化を引き起こす原因となりますが、EPAの作用により血液がサラサラになることで血管への負担が軽減され、若々しくしなやかな血管を保つことができます。
◎中性脂肪値を下げる
中性脂肪といえば健康に良くないとイメージされがちですが、本来は生命維持に欠かせないエネルギー源となる脂肪であるため、ある程度の量を食事から摂取する必要があります。
しかし過剰に摂取すると内臓脂肪や皮下脂肪となって身体に蓄積され、糖尿病や高血圧、高脂血症や動脈硬化などを引き起こす原因となります。
EPAにはこの中性脂肪値を下げる作用があり、健康な身体を維持するうえで重要な役割を担っています。
◎血圧を下げる
EPAが持つサラサラ血液作用によりに血液が流れやすくなることで血圧値を下げる効果を発揮します。
◎血栓の予防
血栓とは血液を固める成分である血小板の固まりであり、心筋梗塞や脳梗塞などの血管疾患を招く原因にもなります。
EPAにはこの血小板の働きを鎮静化させる作用があり、血栓の発生を防ぐことで血管疾患を予防することができます。
◎血糖値を下げる
EPAには血液中の血糖値を下げる作用があり、糖尿病を予防する効果を発揮します。
◎内臓脂肪値を下げる
内臓脂肪が蓄積する原因は血液中の中性脂肪値が高いことにありますが、EPAには中性脂肪値を下げる作用があるため内臓脂肪値を下げる効果もあります。
また内臓脂肪値が下がることで内臓脂肪が原因となるメタボリックシンドロームや皮下脂肪などを改善させる効果もあります。
◎肥満予防
EPAにより中性脂肪値が下がり内臓脂肪が減少することで、肥満を予防する効果があります。
◎運動能力の向上
激しい運動やスポーツを行う際に直ぐにバテてしまったり、持久力がなかなかアップしなかったりする原因の一つは血液にあります。
血液がドロドロの状態であると血流が滞り、手足の先まで酸素が行き届かず身体が酸欠状態となり、直ぐにバテてしまいます。
EPAはドロドロ血液をサラサラにする作用に優れているため、血液がサラサラになると血流も促進され全身に酸素が行き渡るようになり、その結果直ぐにバテず持久力をアップさせることができます。
また血液がサラサラになることで心臓への負担や運動後の疲労が軽減されるという効果もあります。
◎筋肉痛の緩和
激しい運動やスポーツをした後は血液中に炎症物質が発生するほか、筋肉細胞に損傷を受け、疲労や筋肉痛が現れます。
EPAには血液中の炎症物質の発生を抑制する作用や、筋肉細胞の修復を早める作用などがあり、激しい運動やスポーツの後の疲労や筋肉痛を緩和させる効果があります。
◎抗炎症作用
脂肪酸の一種であるEPAは脂肪酸の中でも特に柔らかい性質を持っており、細胞膜に取り入れられることで柔らかな細胞膜を作り出すことができます。
そのほか、細胞膜に取り入れられたEPAが抗炎症物質へと変換されて様々な炎症から身体を保護する効果を発揮します。
◎花粉症やアトピーなどのアレルギー疾患の改善
EPAには免疫機能を調節する作用があるほか、アレルギー反応によって生み出される「ロイコトリエンB4」という炎症物質の生産を抑制する作用があり、さらにアレルギー症状を鎮めるビタミンBの一種・ビオチンの働きを活性化させる作用もあり、花粉症やアトピー性皮膚炎など現代人に多いアレルギー疾患を改善させる効果があります。
◎ドライアイの予防
ドライアイとは、10秒間ほど瞬きを全くせずに目を開けていられない状態のことで、目の表面が乾きやすいことをさします。
EPAには目の健康維持にも働きかけるため、長期に渡り摂取し続けることでドライアイを予防する効果があります。
◎紫外線による肌ダメージを軽減
EPAが持つ抗炎症作用は、紫外線によってダメージを受けた肌の炎症を軽減させる効果もあり、日焼けなどをした際に摂取すると回復を早めることができます。
◎生理痛の緩和
生理時に下腹部の痛みや腰痛、頭痛、嘔吐などの症状が現れる女性も少なくありませんが、これは子宮収縮を促す「プロスタグラシン」という成分が関係しています。
EPAにはこのプロスタグラシンの働きを抑制する作用があるため、生理痛をはじめとする生理時の様々な症状を緩和させる効果があります。
EPAにはこういった作用や効果・効能がありますが、特に血液サラサラ効果、血糖値や中性脂肪値の改善、血圧値の改善など主に血液に働きかける作用に優れているため、生活が不規則で食生活が乱れがちな現代人こそ積極的に摂取したい成分となっています。
また次のような方々にも積極的な摂取が推奨されています。
・いつまでも若々しい身体を維持したい方
・生活習慣病を予防したい方
・スポーツを楽しむ習慣がある方
・アレルギー症状でお悩みの方
・ドライアイでお悩みの方
・生理痛でお悩みの女性
◆DHAとEPAの摂取目安量とおすすめ食材
DHAとEPAは健康を維持するために毎日の摂取が推奨されています。
1日あたりの目安量はDHA・EPAともに900mg以上となっており、次に紹介する食材を参考に毎日の食事に取り入れてみましょう。
◎DHAを豊富に含むおすすめ食材(※食材100gあたりのDHA含有量)
本まぐろ(2,877mg)、真鯛(1,830mg)、ぶり(1,785mg)、さば(1,781mg)、さんま(1,398mg)、さば水煮缶(1,300mg)、いわし水煮缶(1,200mg)、まいわし(1,136mg)、さけ(820mg)、あじ(748mg)、かつお(310mg)、かれい(202mg)
◎EPAを豊富に含むおススメ食材(※食材100GあたりのEPA含有量)
まいわし(1,381mg)、本まぐろ/トロ(1,288mg)、さば(1,214mg)、真鯛(1,085mg)、ぶり(899mg)、さんま(844mg)、さけ(492mg)、あじ(408mg)、かれい(210mg)、ひらめ(108mg)、かつお(78mg)、本まぐろ/赤身(27mg)
DHAとEPAを同時に効率よく摂取するならばフィッシュオイルサプリメントやサメ肝油サプリメントがおススメです。
サプリメントならば生魚をさばく手間がかからず、食生活が乱れていてもDHAとEPAの1日あたりの摂取目安量を手軽に補うことができるので、ぜひ毎日の健康維持のために活用してみて下さい。
DHAとEPAを効率よく取るなら!GMP認可のこちらのサプリメントがおすすめ!